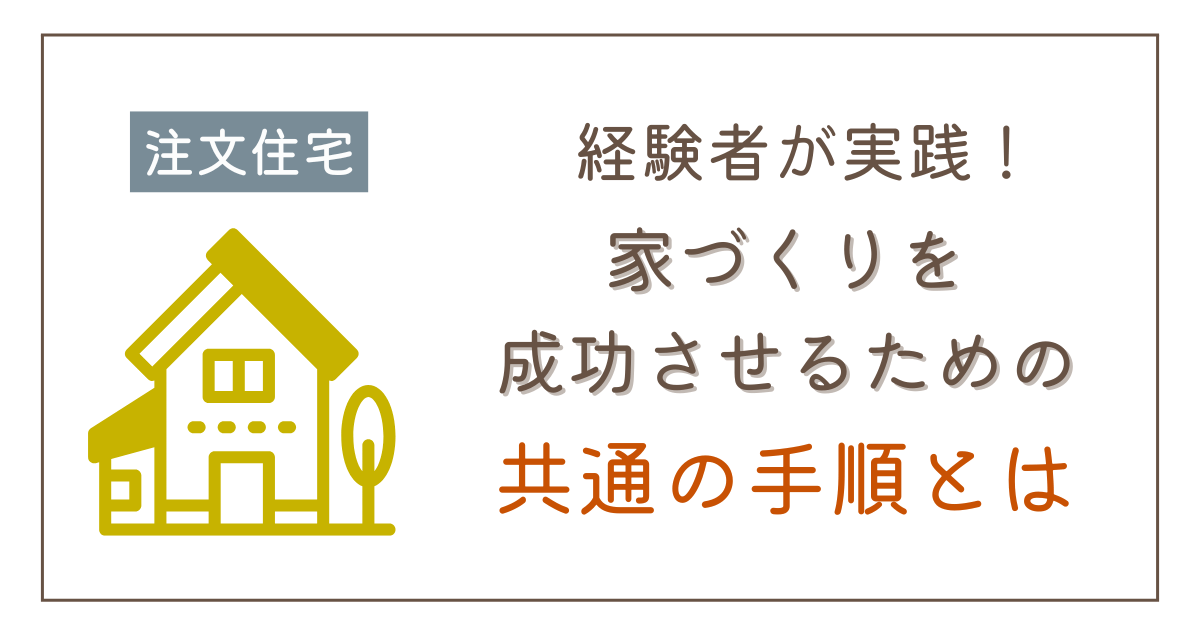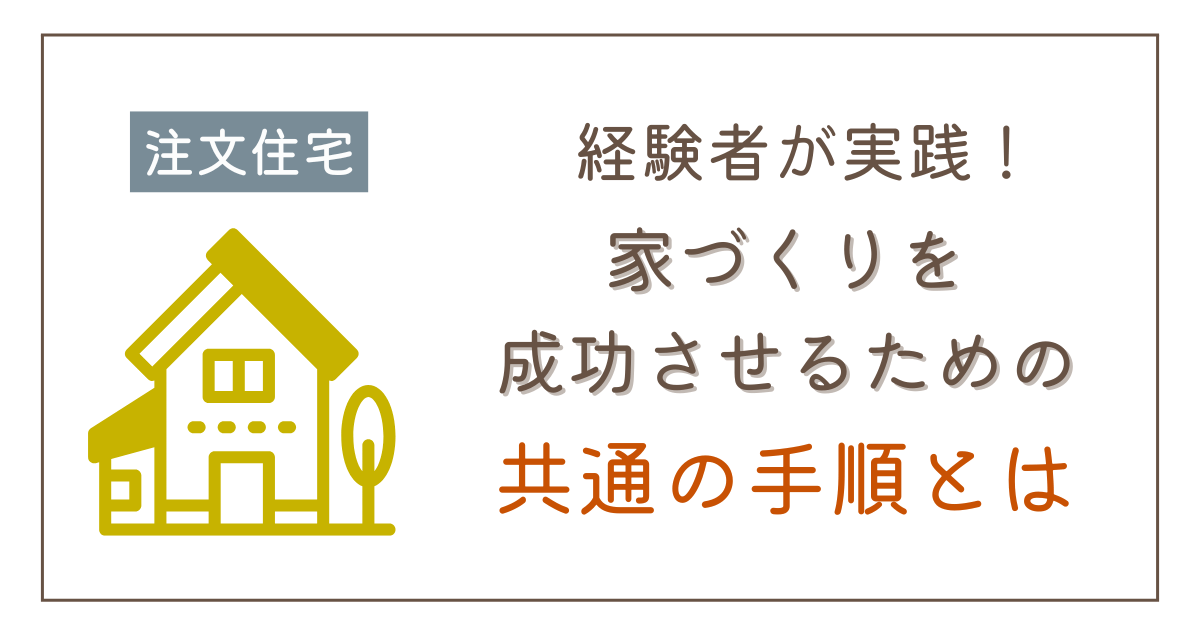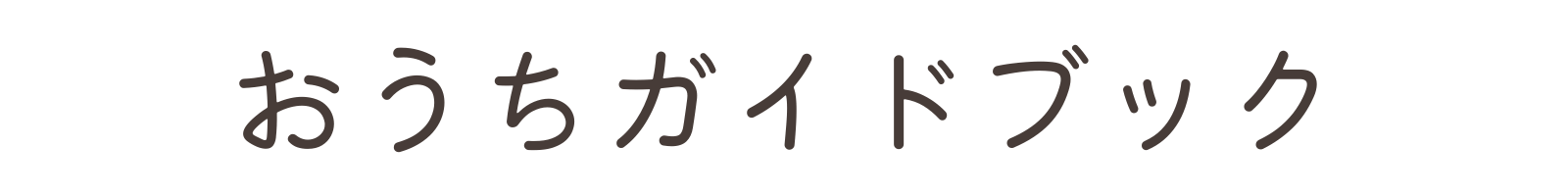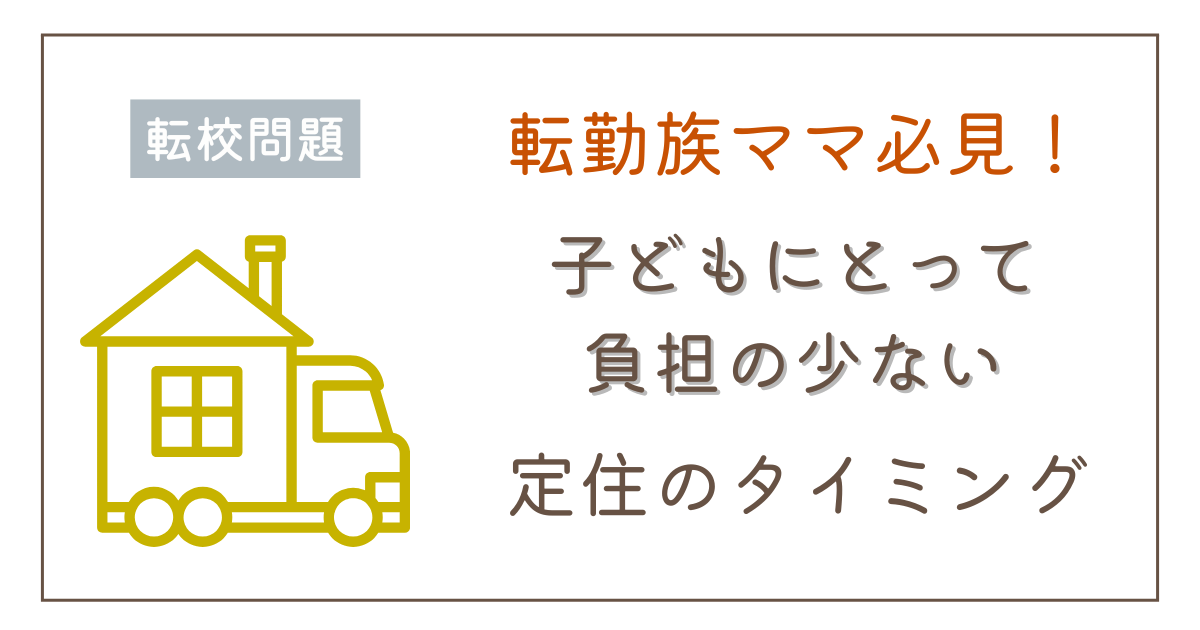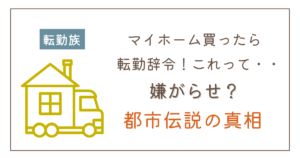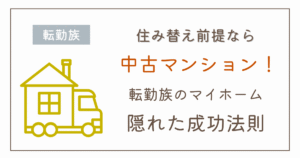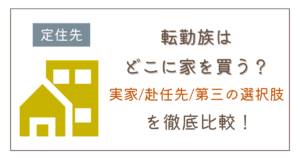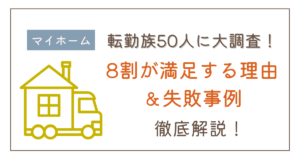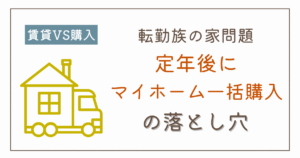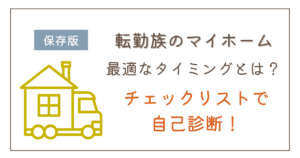転勤族だから、子どもの転校が続くと心配・・
転勤族の家庭にとって、子どもの転校は避けて通れない問題です。
- 何回も転校してかわいそう
- いつ定住すればいいの?



こんな風に不安になる親御さんも多いですよね
そこで本記事では、転校による子どもへの影響を最小限に抑えるための定住のベストタイミングについて詳しくお伝えします。
- 転勤族の子どもにオススメの定住時期
- 親が子どもにできるケアとサポート方法
- 転勤族の子どもが身につけるチカラとは
進学や受験を見据えて迷っている方にも参考になるはずです。
ぜひ最後までお読みくださいね^^


転勤族の家庭で増える転校の悩みとは?
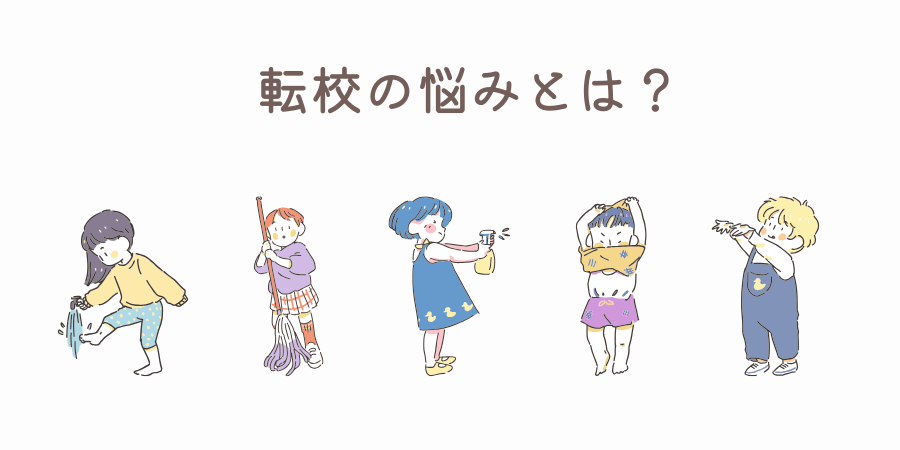
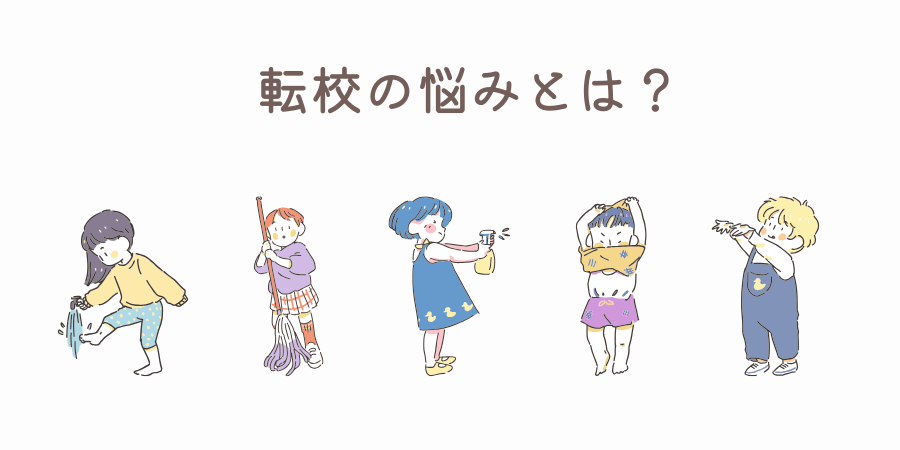
転勤族の家庭にとって、子どもの転校は避けられない課題です。
特に学年が上がるにつれて、転校による不安やストレスは大きくなりがち。
- 友達と離れたくない
- 新しい学校になじめるか不安



こういった声は、子どもの本音としてよく耳にします
そのため、転勤のたびに
- いつ定住するべきか
- このままついていくべきか
今後の生活について悩む家庭も多いのです。
転校が子どもに与える心理的・学習面の影響
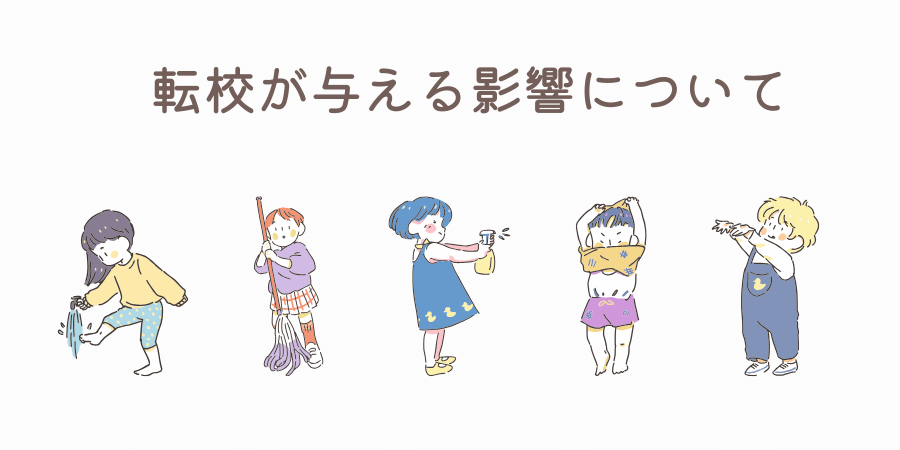
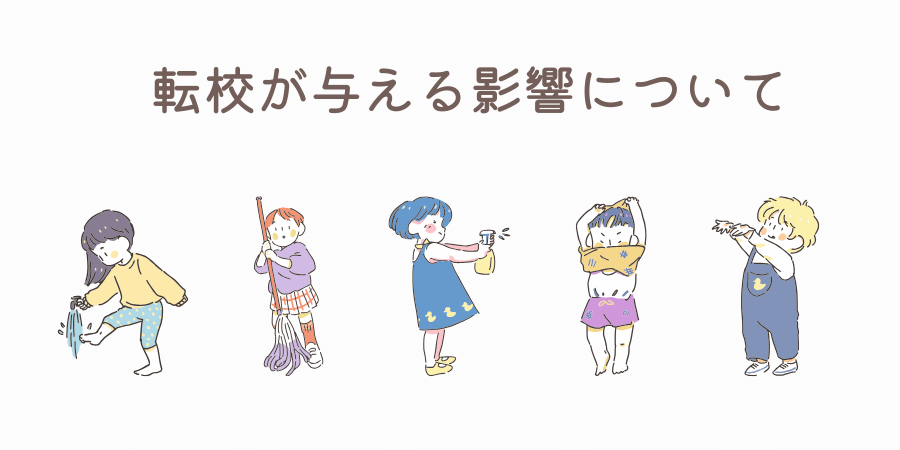
子どもにとって転校は、環境の大きな変化です。
特に小学生・中学生の時期は、友人関係や授業内容の違いに敏感で不安定になりやすい傾向があります。
- 友達作りへの不安
- 授業の進度の違いによる学習の遅れ
- 方言や地域の文化への戸惑い
また、転校を繰り返す中で
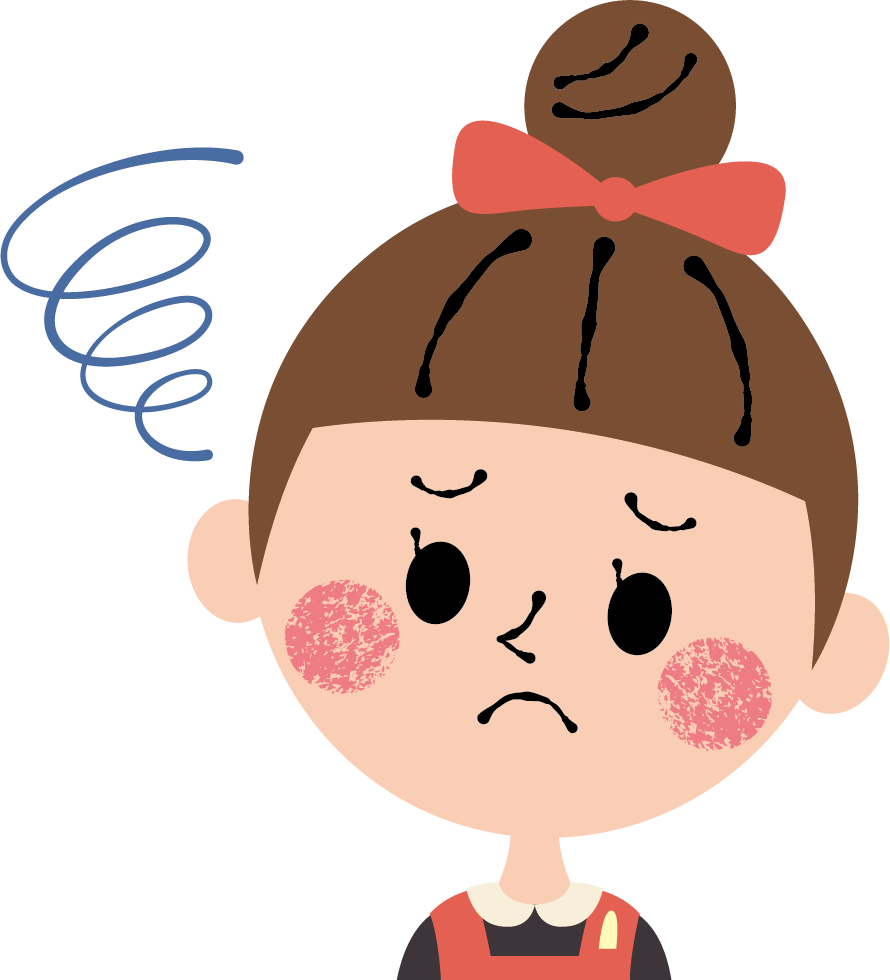
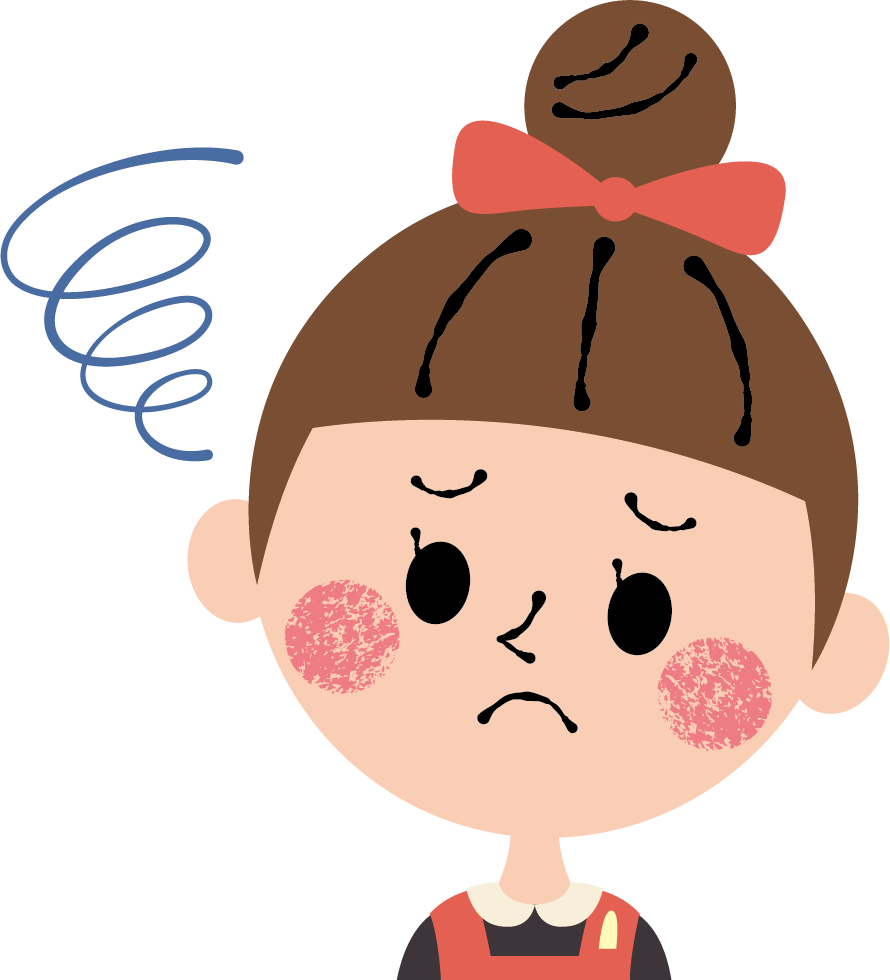
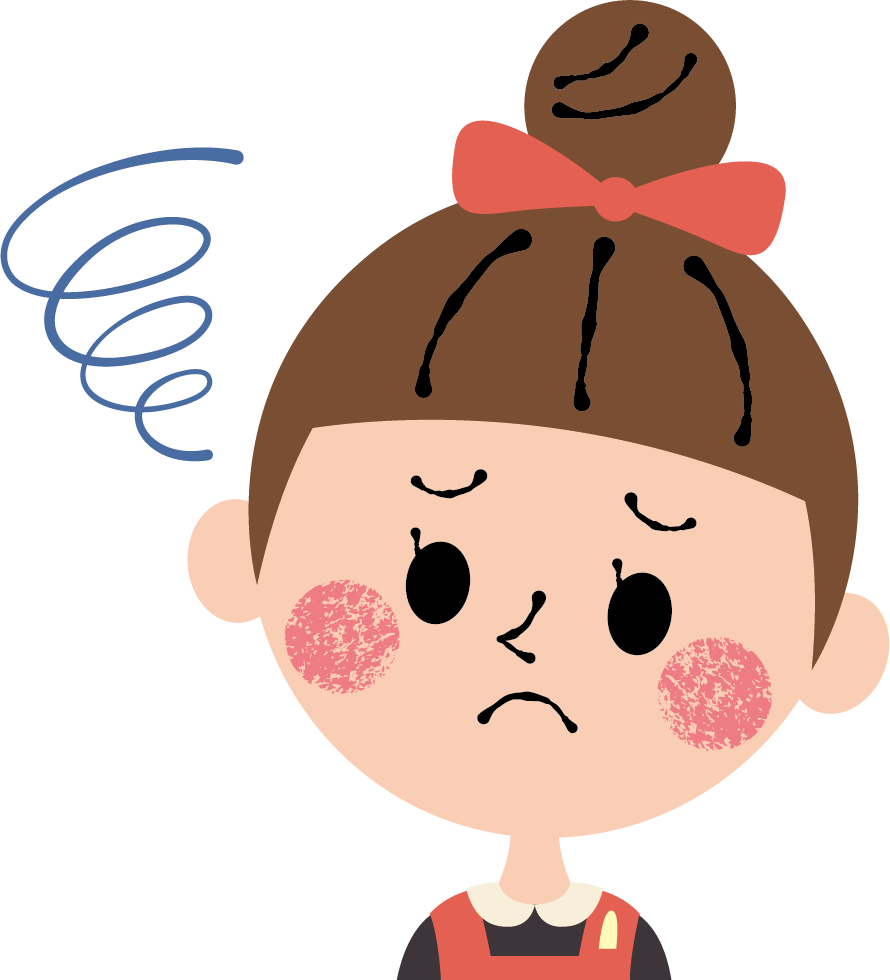
どうせ引っ越すから深く仲良くならないようにしよう
といった心のブロックができてしまうことも。
年齢別|転勤族の子どもにオススメの定住時期
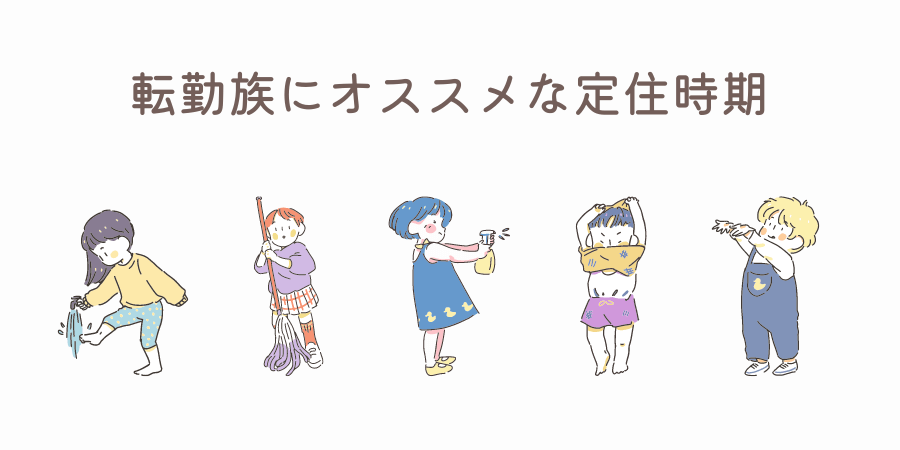
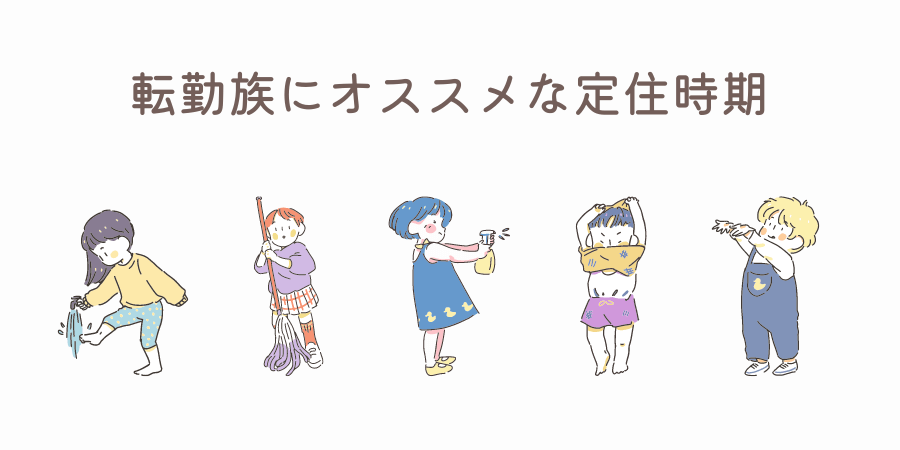
転校は仕方ないとはいえ、なるべく子どもには負担をかけたくないですよね。
その場合のオススメの定住時期は、小学生のあいだです。
- 低学年だと友達関係が浅く、転校の心理的ハードルが低い
- 高学年だと家族の時間も優先できる
- 高校受験に影響がない時期だから
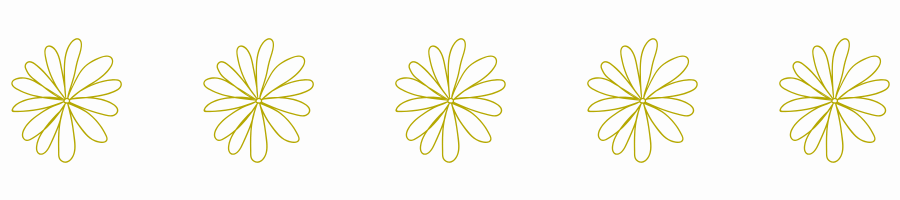
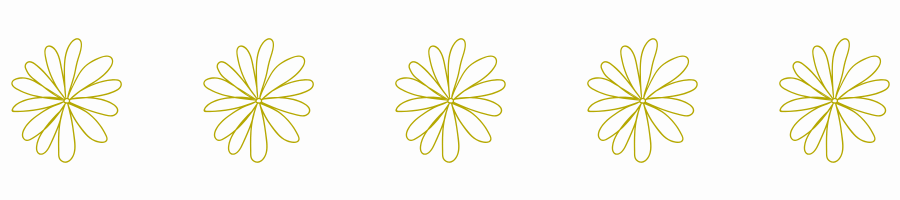
小学校低学年の定住が理想的
特に、小学校入学のタイミングは、転校することなく一貫して同じ学校に通うことができます。
また、小学校低学年のうちは親とのかかわりが深い時期です。
一方で、小学校2~3年生くらいからお友達とのかかわりが増え、友達同士で公園に遊びに行ったりと絆も深まっていく傾向があります。
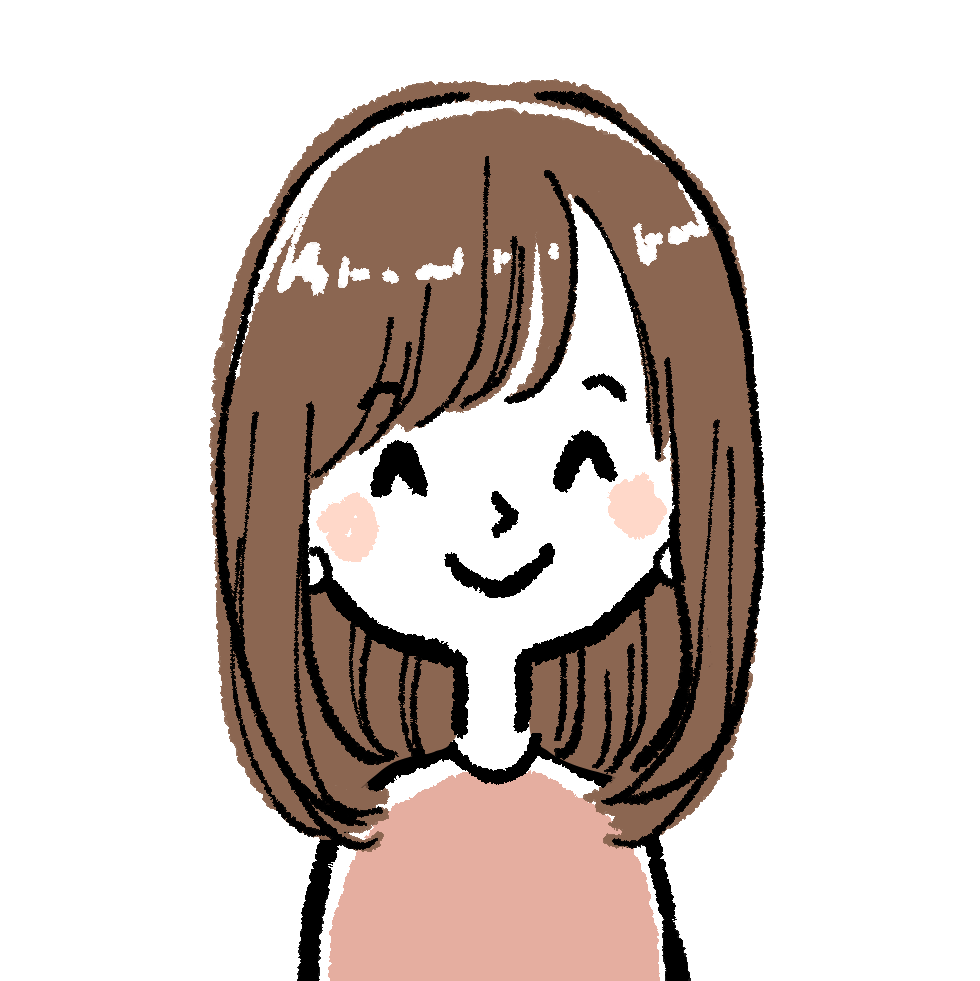
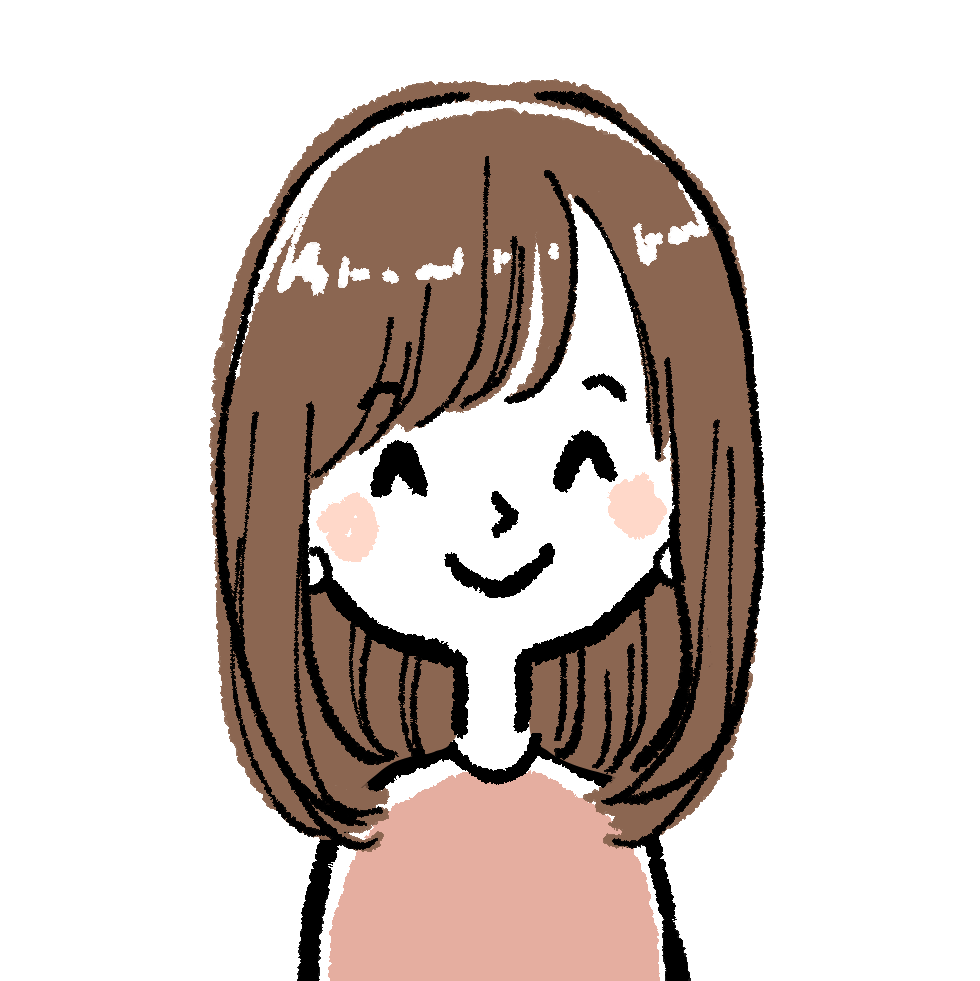
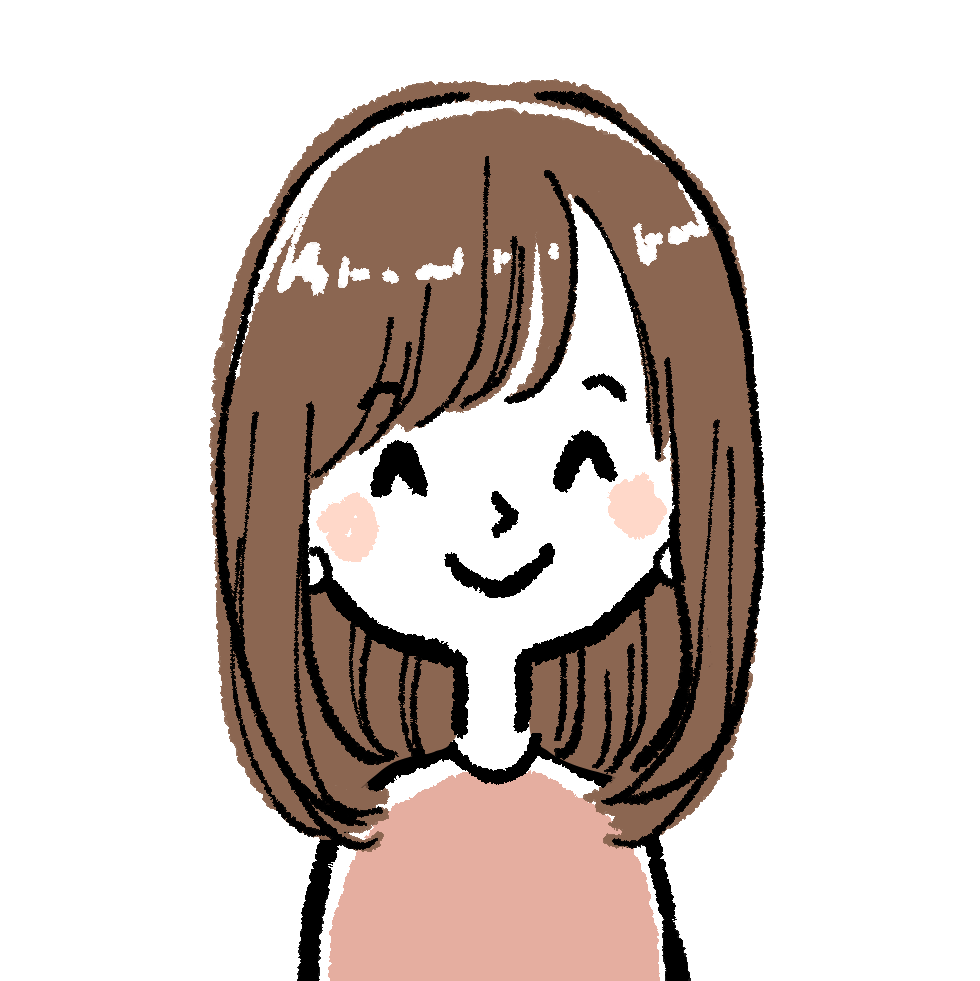
小3の娘も最近は遊ぶお友達が定まってきました
そのため、いずれ子どもが転校を嫌がる時期がきます。
この時期を迎える低学年のうちに定住することで、学校や人間関係での子どもの負担を減らすことができますよ◎
当ブログで独自に行った調査でも、
- 子どもが産まれて賃貸が手狭になった
- 小学校に入学するタイミング
- 子どもが成長し部屋が足りなくなった
- 子どもが転校を嫌がった



こういったリアルな声が聞けましたよ!
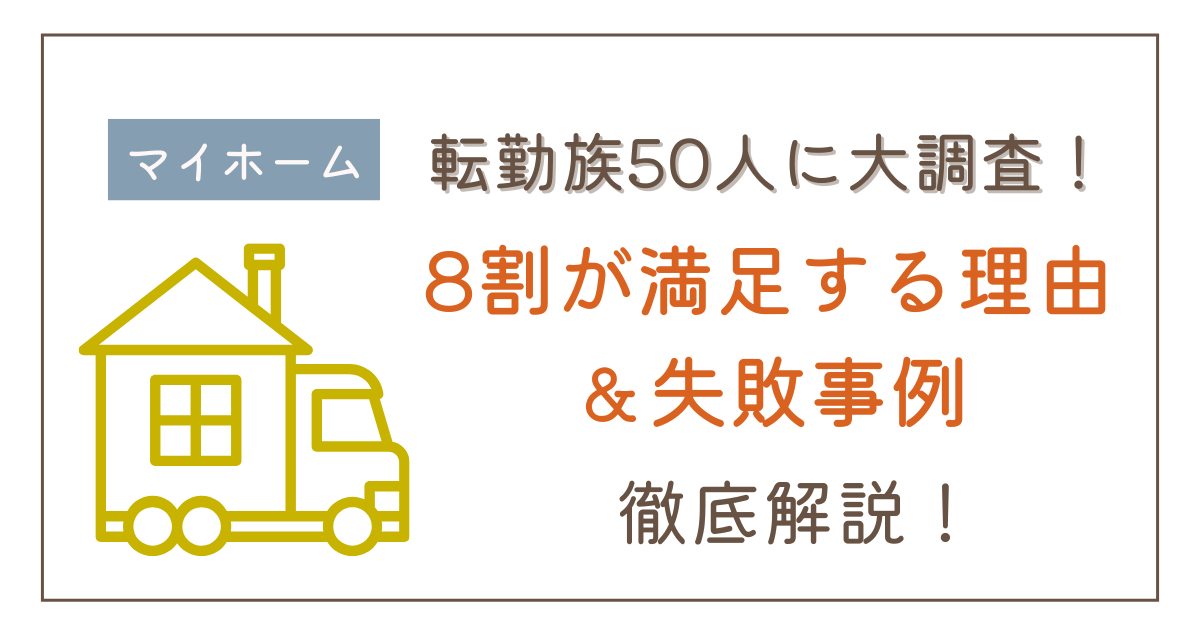
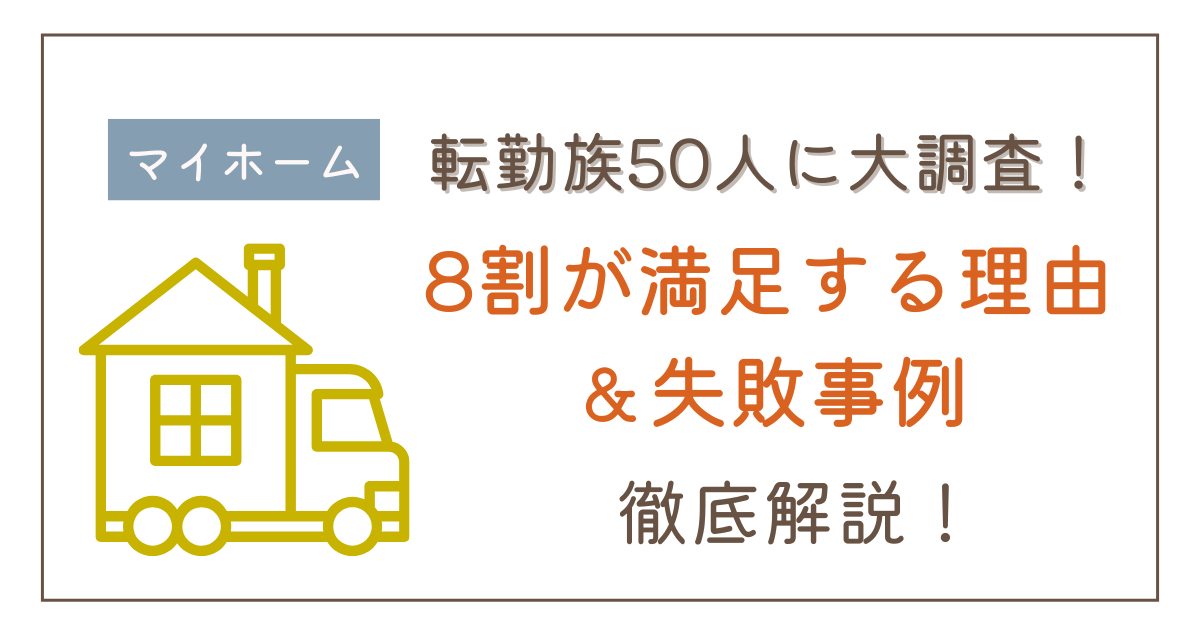
小学校高学年だと家族の時間も優先できる
一方で、小学校高学年での定住を選ぶ家庭もあります。
この時期は、子どもが家族との時間を大切にする最後の時期とも言われています。
定住してしまうと転校は防げますが、単身赴任になる可能性もあり家族の時間が少なくなってしまう可能性も。



特にお子さんがパパ大好きな場合は、悲しい思いをさせてしまうかもしれません
この場合、小学校低学年ではなく高学年で定住を決めることで、家族のかかわりを増やすことができます。
娘は、小3の頃から放課後に友達と遊ぶことが増えました。



子どもはだんだん友達を優先するようになることを、日々実感中です
中学生になると部活も忙しく、家族で出かける機会も少なくなります。
そう考えると、小学生のあいだは親子のかかわりをたくさん持てる最後の時期なのかもしれませんね。
遅くても中学生までに定住すると安心
小学生のあいだの定住が難しい場合は、中学生での定住をオススメします。
理由は高校生での転校はハードルが高いからです。
高校生になると、部活動や受験勉強が本格化し、転校が大きな負担となることがあります。
そのため、遅くても中学生のうちに定住を決めることで、子どもが安心して学業に集中できる環境を整えることができます。
4月転入はスムーズにいきやすい
また、転入の時期ですができれば4月スタートがオススメです。
- 授業の進み具合にズレが起きにくい
- 運動会などの年間行事に参加しやすい
- クラス替えの直後なので、人間関係ができあがってなく馴染みやすい
ただ、小学校6年生の4月に転入した場合はすぐ修学旅行がある可能性も。(一般的に6年生の春か秋)
そのため、修学旅行までに仲の良い友達ができるか心配になる子もいるようです。



高学年だと、小5の4月転入がベストかもしれませんね
転校後の子どもを支える親のケアとサポート方法


そうはいっても、様々な事情で定住が先になる方もたくさんいると思います。
そんなときに親ができることを考えてみました^^
転勤先について前向きな話をする
転校先の環境になじめるかは、誰もが不安に感じる部分です。
そのため、転校先の学校や環境を調べておき、
- どんなクラブがあるかな?
- 近くに遊園地があるね~
- ○○が好きなごはん屋さんがあるよ!
このようなポジティブな会話を心がけると、不安も少し和らぐかもしれません。



親である私たちが転勤を楽しめていれば、その気持ちが伝わりますよ!
家庭内に安心できる雰囲気を
「学校どうだった?」と聞きすぎるよりも、子どもが自然と話したくなるような雰囲気づくりが大切。
実は、わが家の子ども達は普段学校での出来事を良く話してくれます。
私が子ども達の話を聞くときに気をつけていることは、
- まずは共感し、子どもの気持ちを否定しない
- 子どもの気持ちを言葉に表す
- なるべく遮らずに、聞く側に徹する
この3つです。
そのせいか、娘も息子も自分からよく話してくれるのですが、私が思っているよりもたくさん学校で頑張ってるんだなと感じることも・・
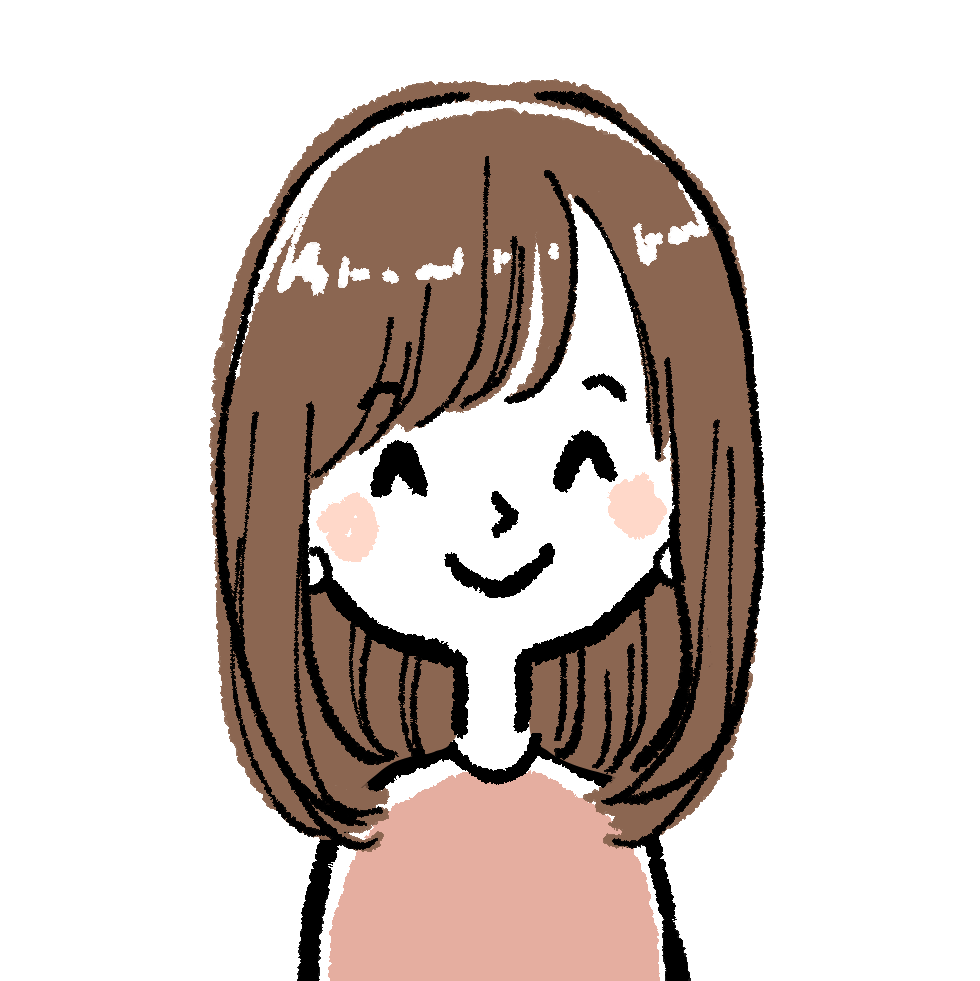
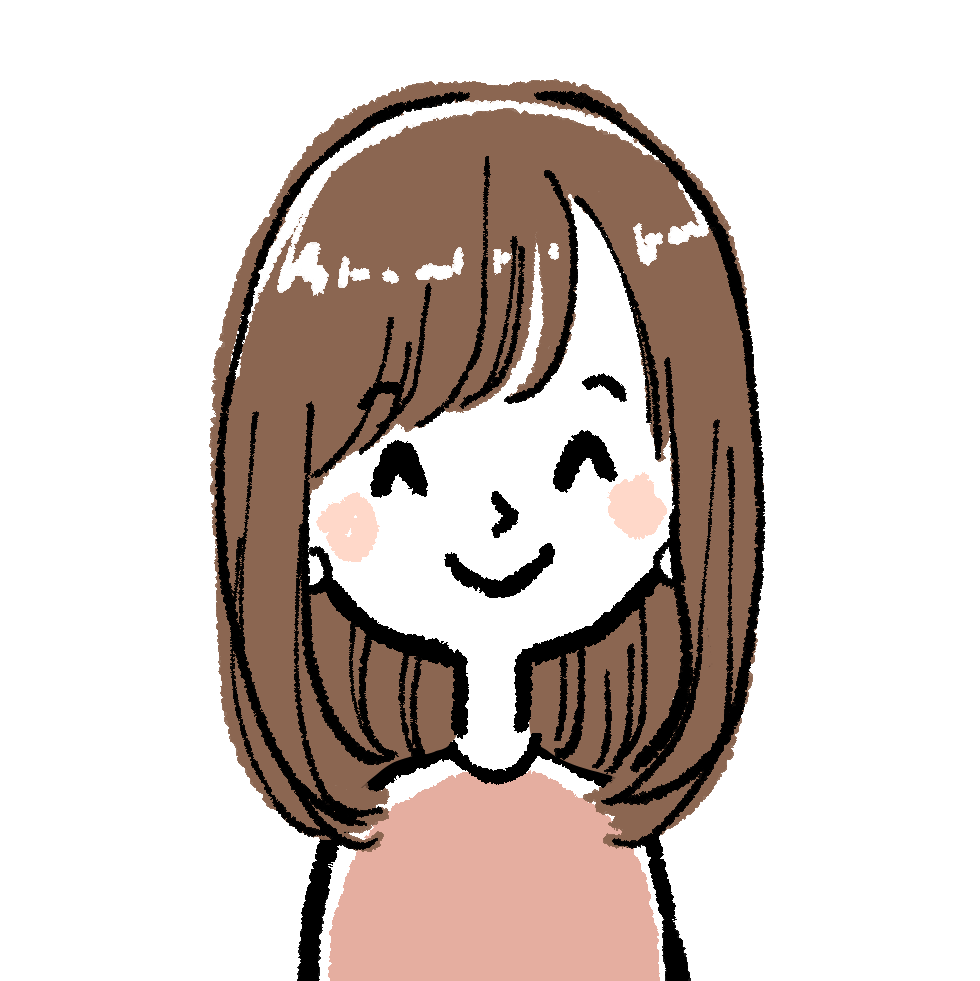
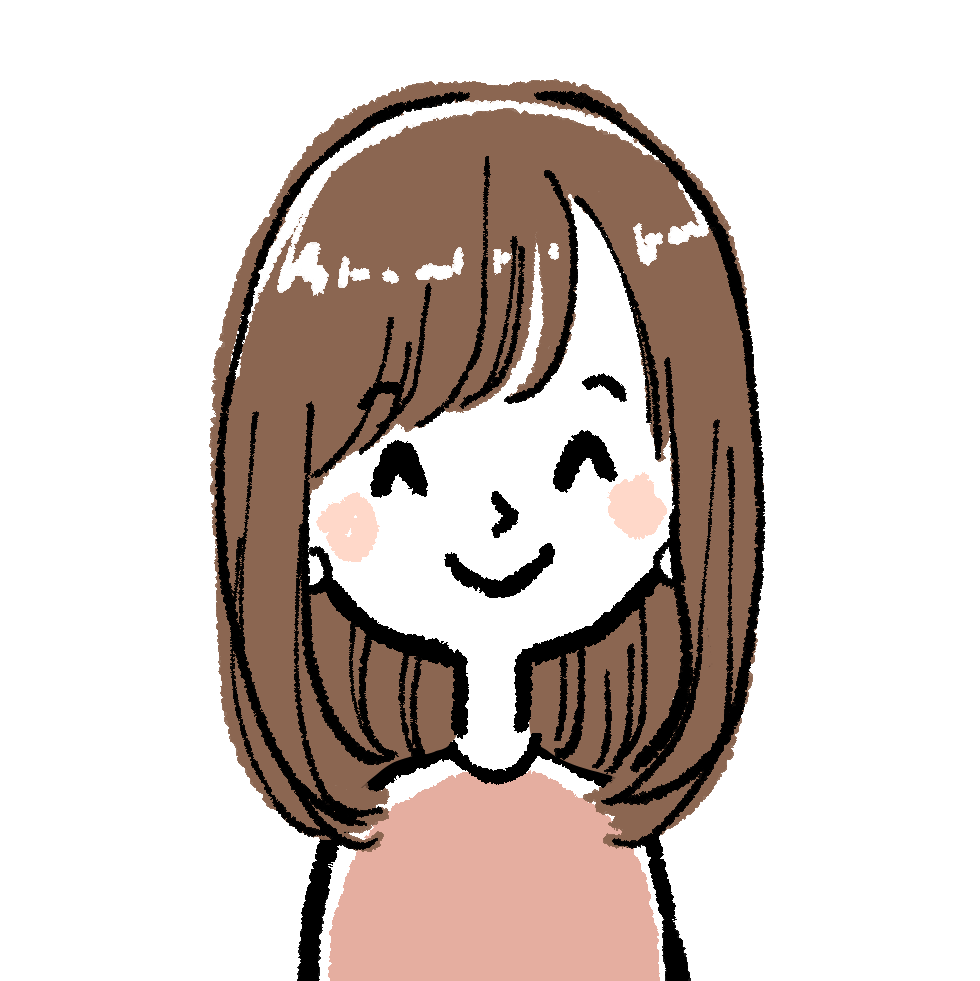
家ではガミガミ怒らないでおこうと思えます笑
転勤族の子どもが身につけるチカラとポジティブな面


転校の経験が多い転勤族の子どもは、その特殊な環境から身につくチカラがあります。
順応性が育つ
新しい環境に慣れる機会が多いため、周囲をよく観察して適応する力が育まれます。
親が転勤族の場合、子どもはお友達と突然の別れを経験します。
そして、転校のたびに新しい学校や友達との生活に切り替えていかなくてはなりません。
こういった経験を繰り返すうちに周りをよく見てその都度うまく溶けこむ力が備わるようです◎
家族の絆が深まる
お友達とは引越しのたびにお別れだけど、どこに行っても家族だけは一緒ですよね。
子どもと同じで親も新しい環境に慣れるのは大変で、引越しの準備も家族の協力が必要不可欠です。
そんな経験を何度も乗り越えていくうちに、家族の仲は深まりやすいようです◎
社交性・柔軟性が身につく
人との出会いと別れを何度も経験することで、どんなタイプの人ともフラットに接する力がつくと言われています。
転校が多いと、仲良くなっても数年経つと別れが待っています。
そういった経験を積んでいくうちに、深い付き合いを避ける傾向があるようです。
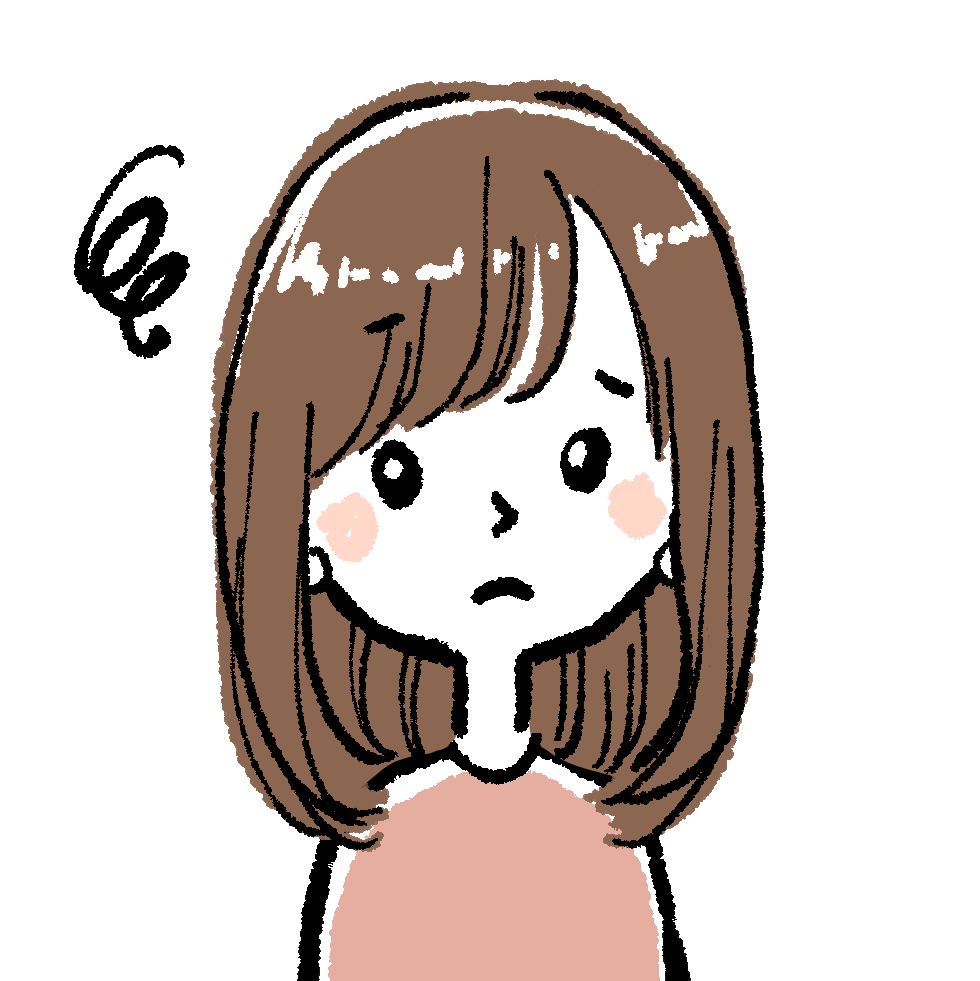
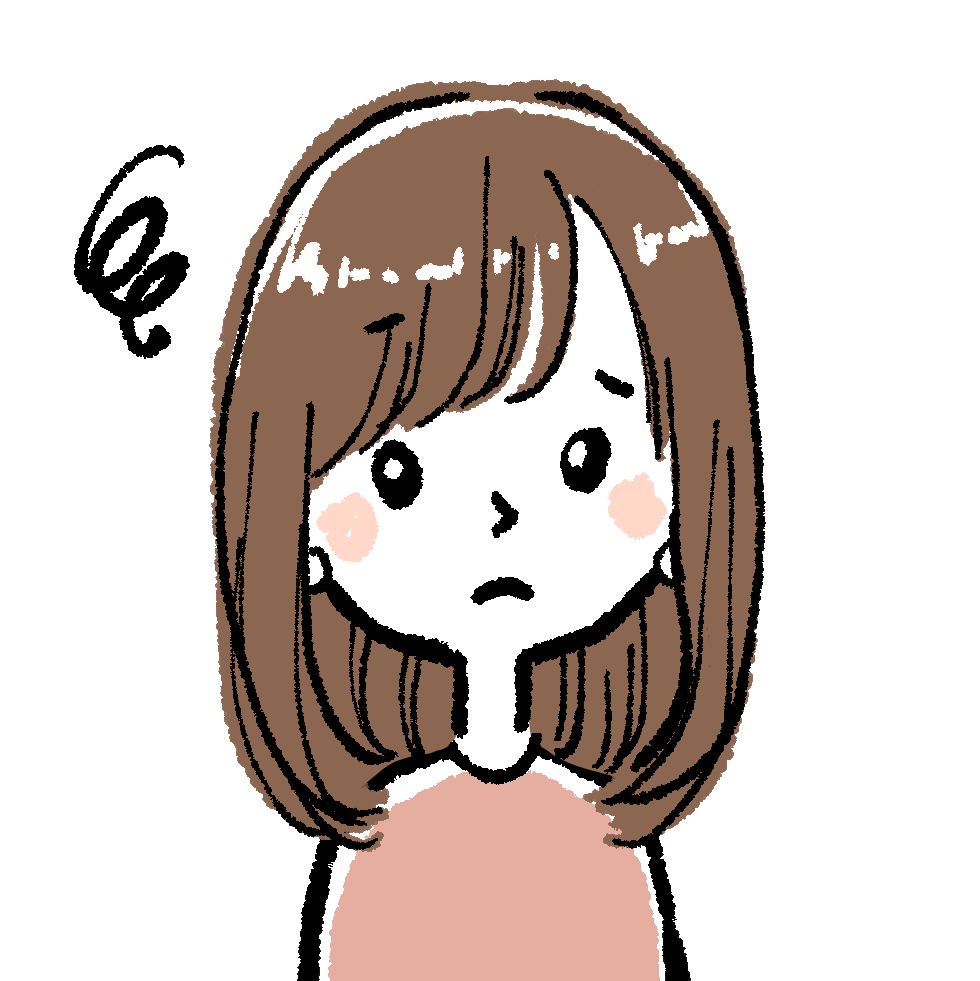
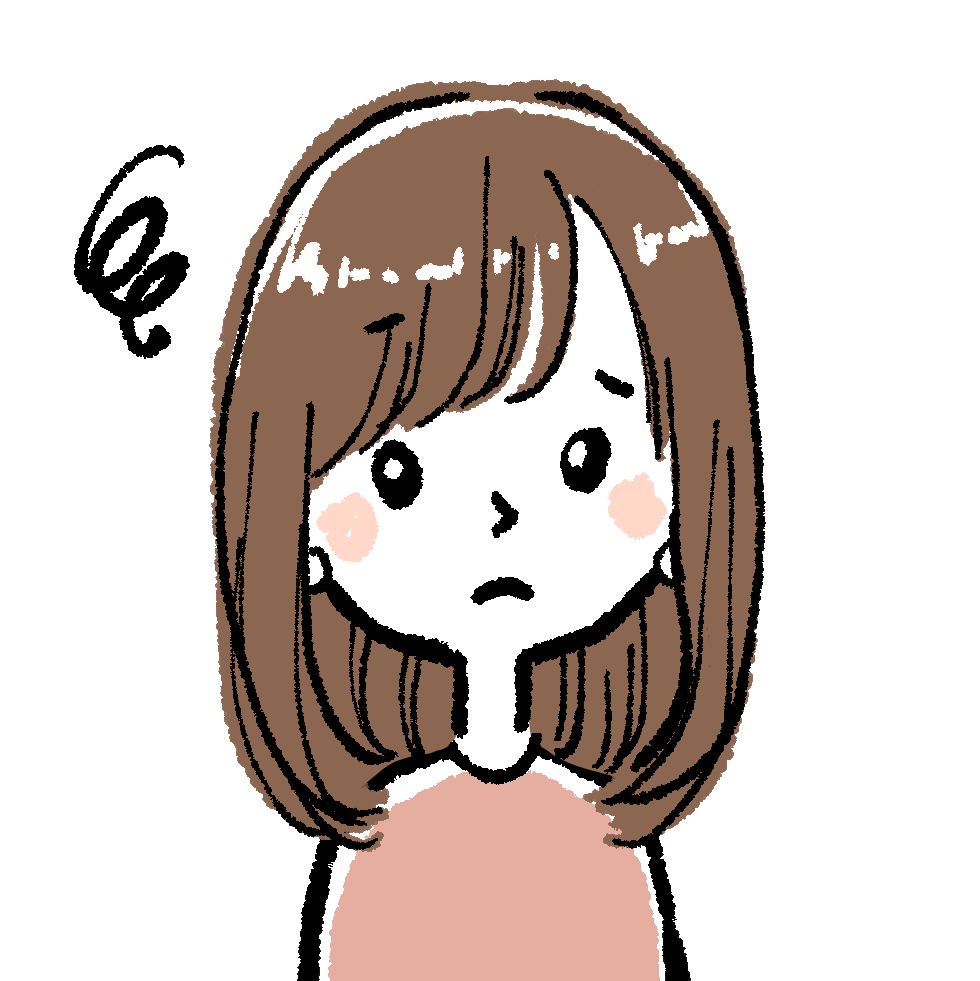
深い仲になってしまうと、お別れのとき余計に寂しいですよね
この傾向は、言い換えればどんなタイプの人とも仲良くなれるということ。
いろいろな環境を経験したおかげで視野が広く、柔軟に対応する力が身につくのかもしれません。
子どもと向き合って最適な定住の時期を見極めよう
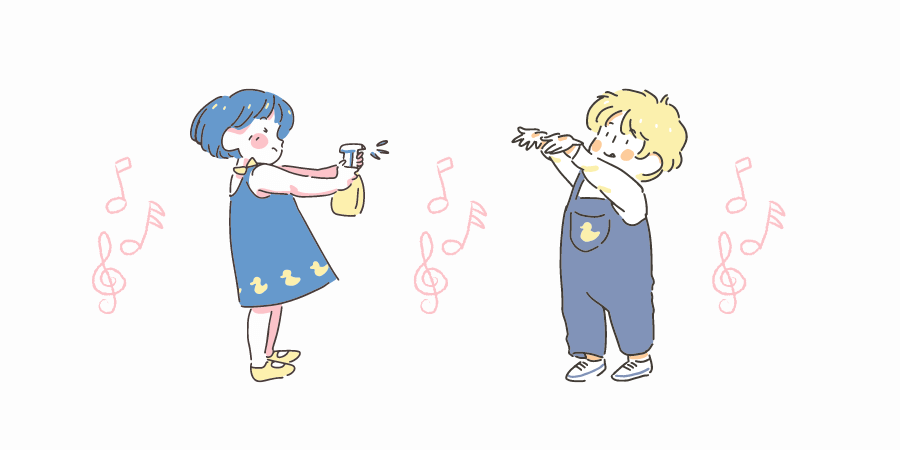
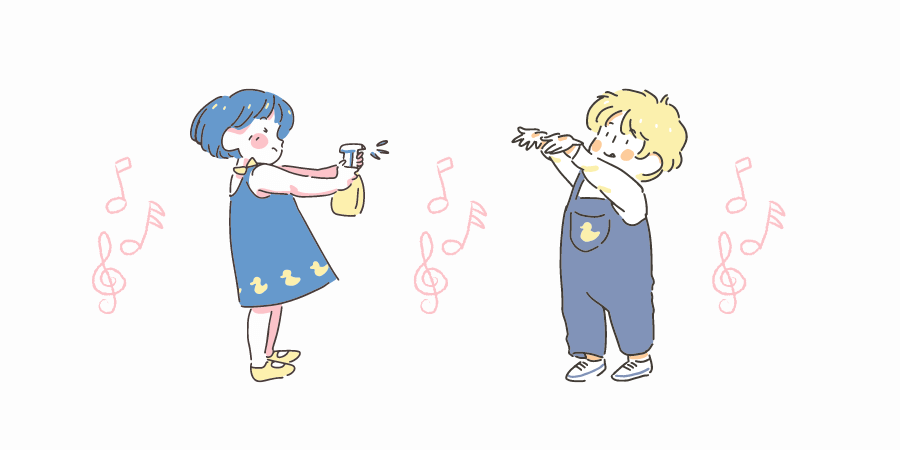
ここまで読んでくださりありがとうございます。
この記事では、転校の多い子どもの特徴と転勤族の子どもにとってベストな定住時期についてお伝えしました。
- 小学生のうちに定住
→ 友達との関係が浅いうちに定住することで、転校のストレスを軽減 - 中学生までに定住
→ 受験や学業への影響を考慮し、中学生までに定住を決めると安心 - 4月の転入
→ 新学期のタイミングでの転入は、子どもが馴染みやすい
転勤族の子どもにとって、転校は負担になる反面、順応性や社交性といった大きな力を育ててくれる経験にもなります。
しかしながら、子どもの年齢や性格・進学のタイミングを見極めながら、いつ定住すべきかを家族でしっかり話し合うことが大切です。
「転勤族だからこそできる柔軟な選択」を活かしながら、子どもにとって最適な環境を整えてあげてくださいね^^


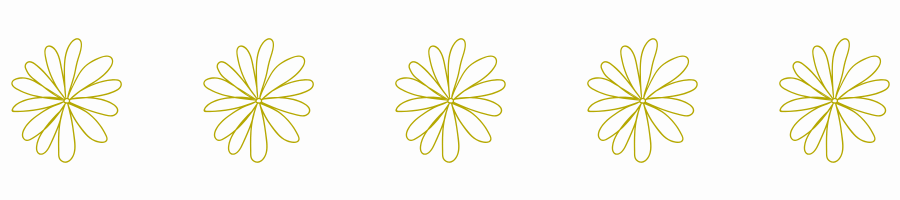
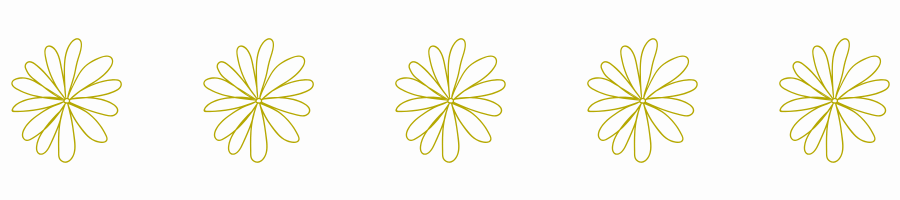
具体的なマイホーム計画の進め方はこちら