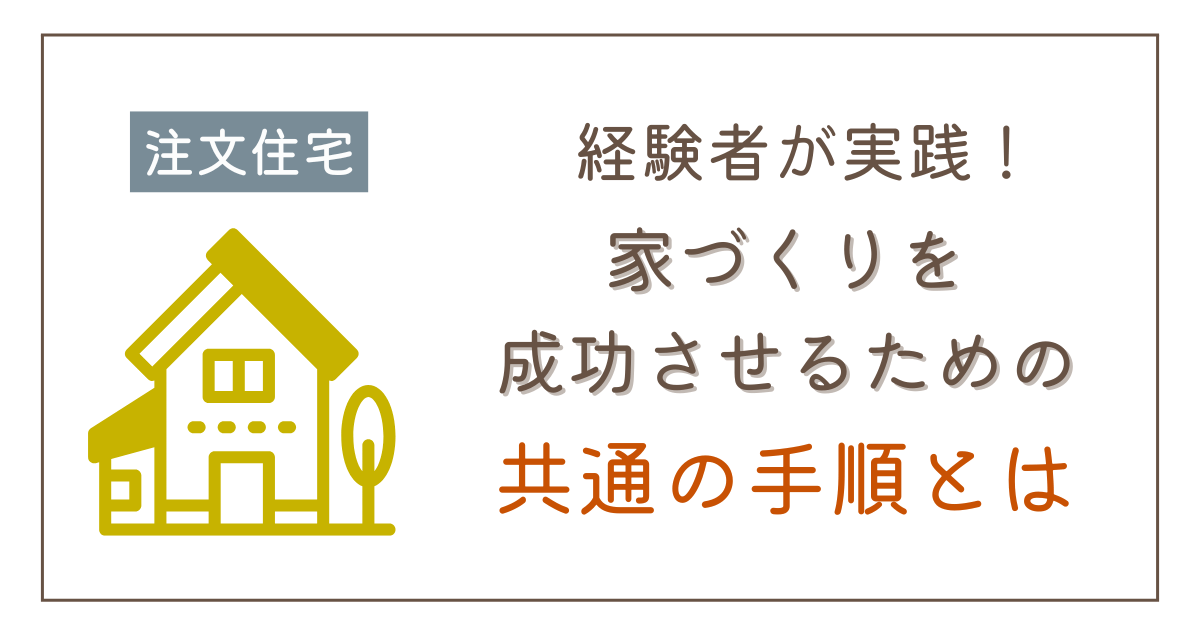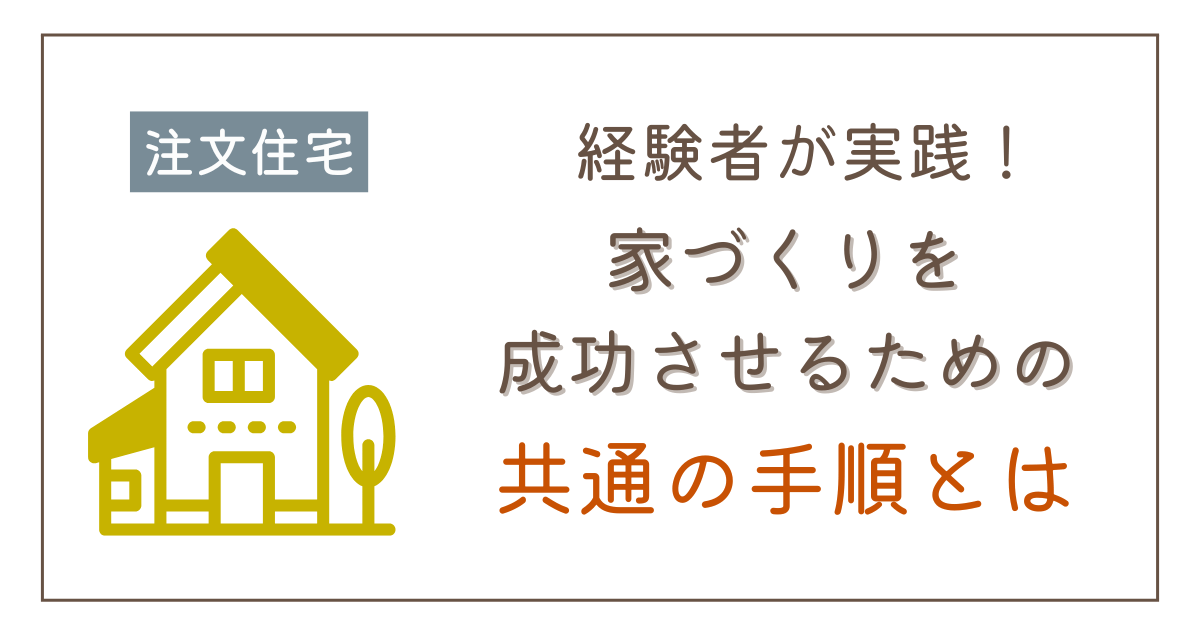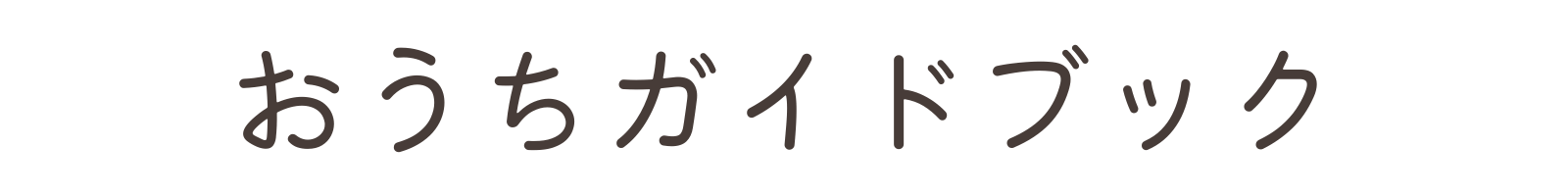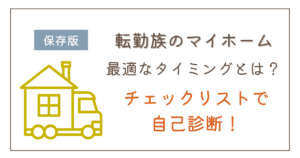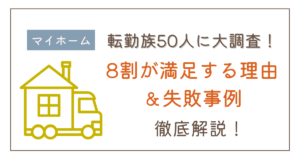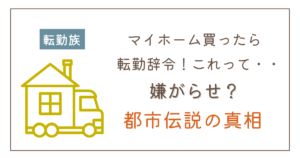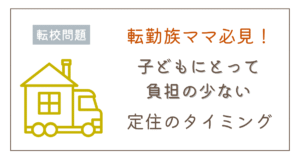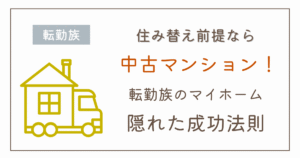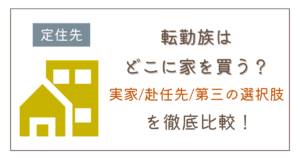転勤族は定年まで賃貸がいい?いつマイホームを購入するべきか悩む・・
転勤のたびに引っ越しを繰り返す日々。
新しい環境に慣れるのも一苦労なのに、家探しのストレスも加わって心身ともに疲れていませんか?
そんな中で頭をよぎるのが“いつかはマイホームが欲しい”という思い。でも、
- 転勤族だから無理
- 定年まで賃貸で我慢するべき
このように諦めている方も多いのでは?



実は今、転勤族でも定年前に積極的にマイホームを購入する人が増えています!
しかも30代や40代で決断する方も多く、転勤中は賃貸に出すなど柔軟な活用をしている方も。
一方で、”定年まで賃貸”を選択し、後から後悔する方も少なくありません。
そこでこの記事では、転勤族が”定年まで賃貸”を選ぶべきかそ・れとも早期購入するべきかを徹底比較します。
この記事を参考に、後悔のない選択をしてくださいね◎


転勤族が定年まで賃貸を選ぶ理由とその落とし穴
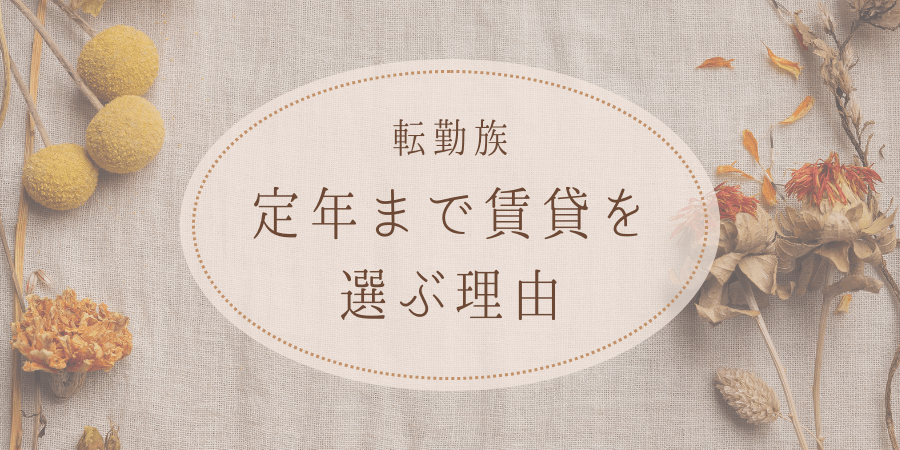
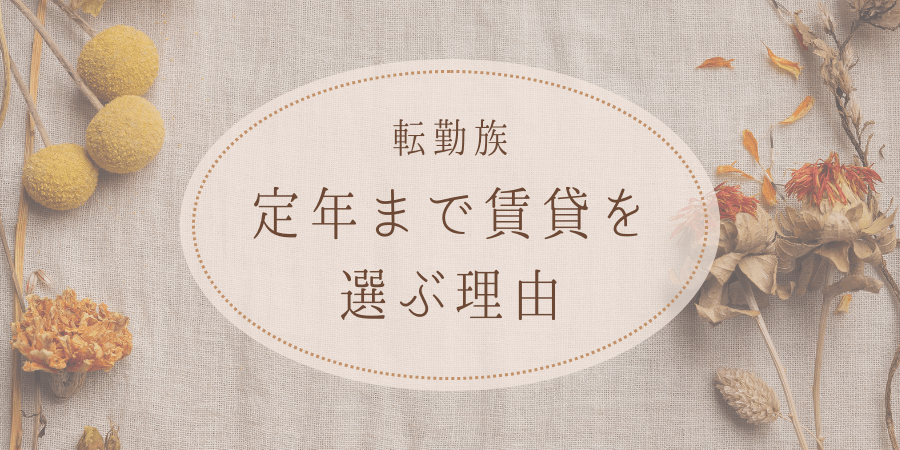
なぜ転勤族は定年まで賃貸を選ぶのか
転勤族が”定年まで賃貸でいい”と考える理由は、実は明確です。
最も多いのが“住まない家にローンを払うのは無駄”という考え。
購入したあとに転勤が決まったら、マイホームに住めなくても住宅ローンを返済しなくてはなりません。



抵抗を感じてしまうのも仕方ないですよね
次に“いつ転勤があるか分からない”という不確実性です。
購入後すぐに転勤辞令が出たらどうしようという不安が、決断を鈍らせています。
さらに“定年後に退職金で一括購入すればローン不要”という計画的な考え方。
定年まで賃貸で過ごし、まとまった退職金で現金購入すれば、金利負担もなく老後の住まいが確保できるというものです。
これらの理由は、一見するともっともに聞こえますよね。



しかし、この選択には見えにくい大きな落とし穴が潜んでいるのです!
“定年まで賃貸”の3つの落とし穴
落とし穴1|消えていく家賃という支出
例えば、月10万円の家賃を30年間払い続けると総額3,600万円になります。
この金額は、完全に消費されるだけで何も資産として残りません。
一方、同じ金額を住宅ローンの返済に充てれば、土地と建物という実物資産が手に入ります。
- 賃貸は”住むための対価”
- 購入は”資産を買うための投資”



この違いは30年後に大きな差となって現れます!
落とし穴2|インフレリスクへの無防備
近年の物価上昇を見れば分かるように、長期的にインフレは進行します。
”インフレーション”の略で、物価が継続的に上昇すること。
同じ金額で買えるモノやサービスの量が減り、お金の価値が下がる状態。
20年後・30年後の家賃がどれだけ上昇しているかは予測できません。



人気エリアでは、需給バランスから家賃が大幅に値上がりする可能性も!
もし定年後、年金生活になってから家賃が上昇すれば生活を圧迫してしまいます。
収入が減る時期に固定費が増えるのは、非常にリスクの高い状態なのです!
落とし穴3|定年後の住宅購入の困難さ
60歳を過ぎてから住宅を探すのは、想像以上に大変です。
さまざまなリスクから、高齢者への賃貸を断られるケースは増えます。
また、購入しようにも年齢や健康状態によって住宅ローンが組めない場合もあります。
退職金で一括購入する計画も、予定通りの金額が出るとは限りません。
- 会社の業績悪化
- 早期退職
- 想定外の教育費 など



計画が崩れる要因はたくさんあります
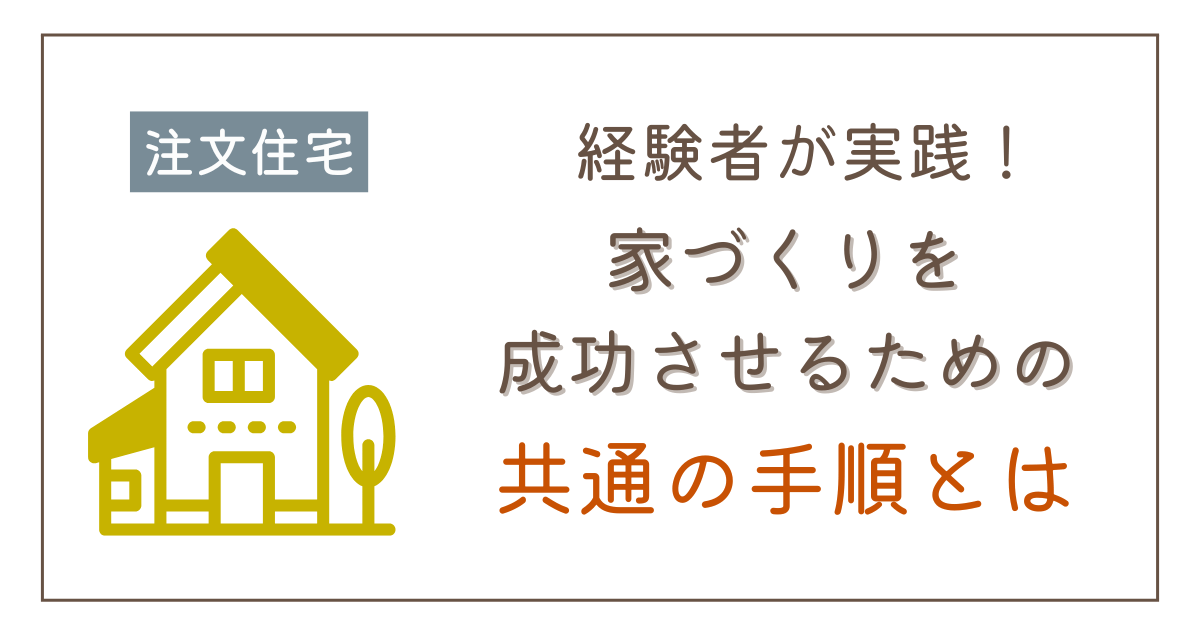
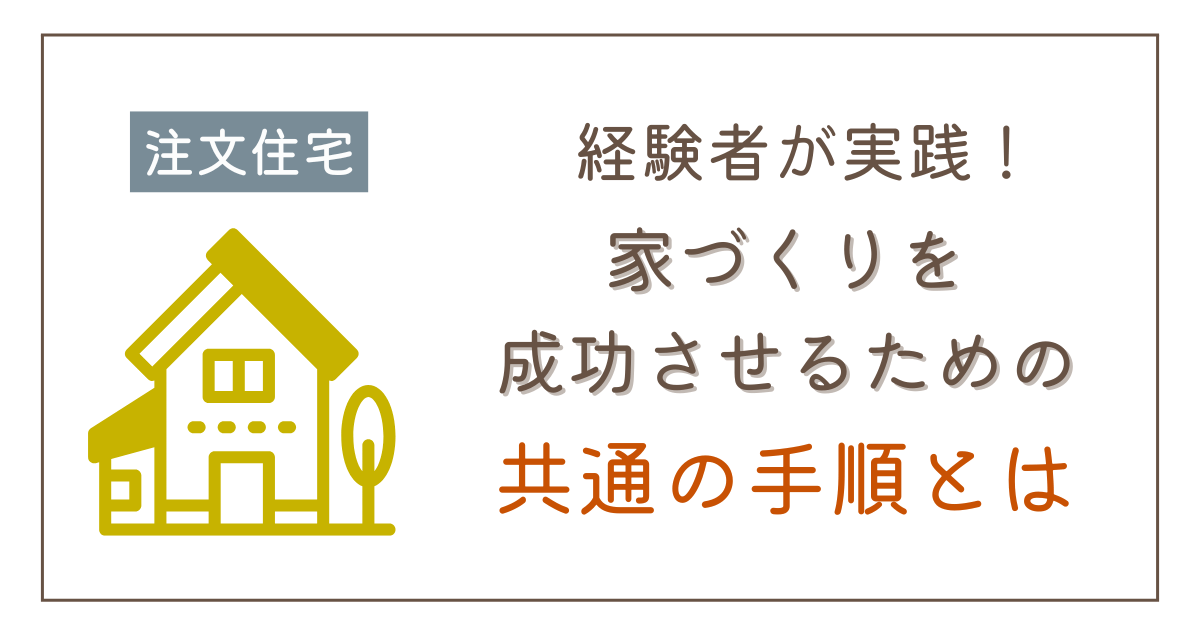


定年まで賃貸vs今すぐ購入|30年間の総コスト比較
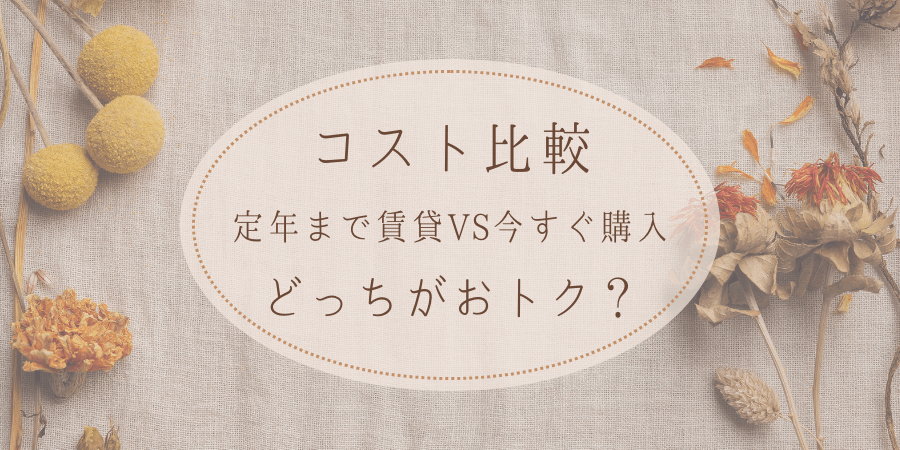
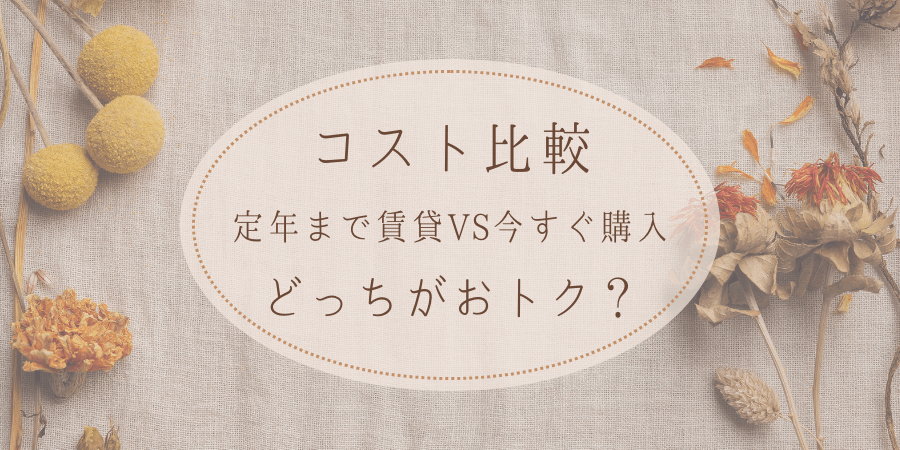
実際に、定年まで賃貸と早期購入ではどのくらいコストの違いがあるのでしょうか?
以下の条件でシュミレーションをしてみました。
- 定年まで賃貸に住む場合
- 40歳でマイホーム購入した場合
- 40歳でマイホーム購入後、賃貸に出した場合
1.定年まで賃貸を続けた場合
- 家賃:月10万円
- 30年間の総家賃:3,600万円
- 更新料(2年ごと):約150万円
- 引越し費用(転勤5回):約150万円
この場合、総支出は約3,900万円。



手元に残る資産はゼロ
賃貸生活では、約4,000万円近い金額を支払っても何も資産として残りません。
定年後も住居費は継続して発生します。
2.40歳でマイホームを購入した場合
- 物件価格:3,500万円
(頭金500万円、借入3,000万円) - 住宅ローン返済(35年・金利1.5%)
約9.2万円/月 - 30年間の総返済額:約3,300万円
- 固定資産税・修繕積立(30年):約600万円
この場合、総支出は約4,400万円。



物件が資産として残ります
(推定価値2,000万円以上)
一見すると購入の方が500万円ほど支出が多く見えますが、重要なのは”手元に資産が残る”という点です。
さらに、転勤中に賃貸に出した場合の収入も考慮してみましょう。
3.購入して転勤中は賃貸に出した場合
- 購入条件は同上
- 転勤期間:15年間(30年のうち半分)
- 賃貸収入:月8万円×12ヶ月×15年=1,440万円
- 管理費・空室期間を差し引いた実収入:約1,200万円
この場合、実質の総支出は約3,200万円。



実質的な支出は賃貸生活よりも少なくなり、さらに2,000万円以上の資産が残ります
トータルで見ると1,500万円以上の差が生まれるのです。
住宅ローン減税の効果も忘れずに
さらに、住宅ローン減税による税制優遇も大きなメリットです。
これは、賃貸生活では絶対に得られない恩恵です。
この減税効果を加えると、購入した場合の実質的な支出はさらに少なくなり経済的メリットは一層明確になりますよ◎
転勤族が定年前にマイホームを持つべき5つの理由
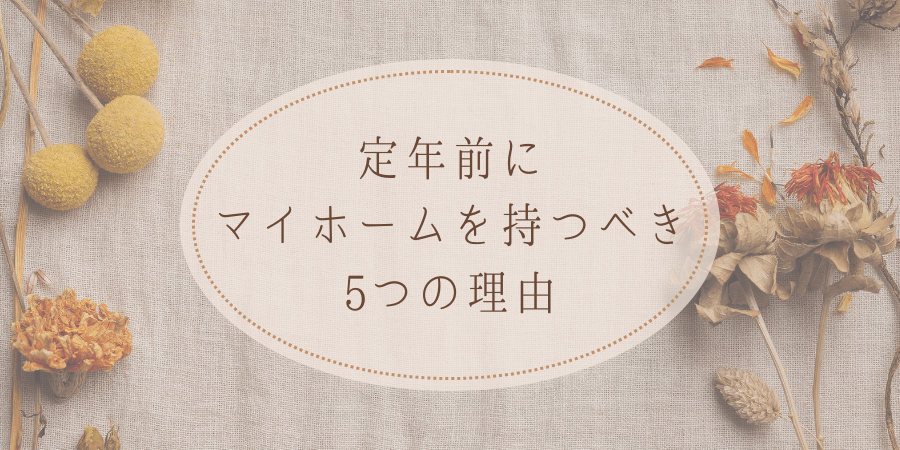
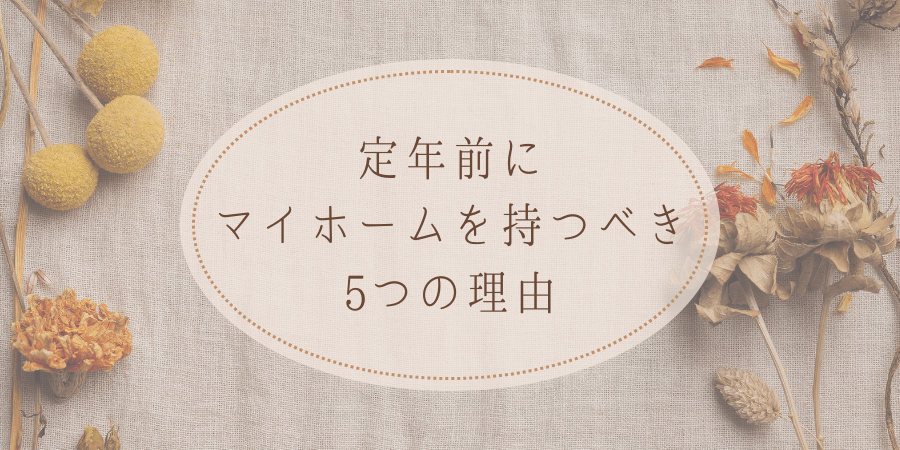
1.家族に”帰る場所”ができる精神的安定
転勤族の最大の悩みは、家族が環境変化に振り回されることです。
特に子どもの転校は大きなストレスになってしまうかも・・



友達と別れ、新しい学校に馴染むまでの苦労は計り知れない!
マイホームを購入すれば、単身赴任という選択肢が生まれます。
家族は慣れ親しんだ地域に残り、子どもは同じ学校に通い続けることができます。
転校のストレスから解放され、友人関係も継続できるのです。
また“ここが我が家”と言える場所があることは、家族全員の精神的安定につながります。
転勤で各地を転々としても、”あそこに帰れば自分の家がある”という安心感は何物にも代えがたいもの。
週末に家族の待つマイホームに帰る。
そんな生活スタイルが、家族の絆をより強くすることもあります。



離れている分、一緒に過ごす時間をより大切にできるという声も多く聞かれますよ!
2. 資産形成と老後の住まいを同時に実現
先ほどお伝えしたように、マイホーム購入は資産形成の有効な手段です。
毎月の支払いが将来の資産になっていくという点で、賃貸とは根本的に異なるのです。
特に立地の良い物件を選べば、将来的に資産価値が維持されたり、上昇したりする可能性も!



都市部の人気エリアや駅近物件などは、需要が高く価値が下がりにくい傾向です◎
定年後は住宅ローンが完済されているか、残債が少ない状態で自分の家に住めます。
老後の住居費負担がほとんどなくなることは、年金生活における大きな安心材料です。
3. 転勤中は収益物件として活用できる
転勤中に賃貸に出せば、家賃収入を得られます。
住宅ローンの返済に充てれば、実質的な負担を大幅に軽減できます。
立地が良ければ、家賃収入がローン返済額を上回り、収益物件として機能することも◎
信頼できる不動産管理会社に任せれば、遠方にいても安心して賃貸経営ができますよ。



管理費用は家賃の5〜10%程度が相場ですが、その価値は十分にあります!
つまり、マイホームは”住む場所”であると同時に”収益を生む資産”にもなり得るということ。
これは、賃貸生活では絶対に得られないメリットです。
住宅ローンを利用中の場合は、必ず借りている金融機関に相談してください◎
住宅ローンは自分が住む家のために借りるお金のため、返済中は賃貸に出すことは原則禁止。
ただし、事前に相談すれば転勤中の賃貸契約はやむを得ないと判断されて認められることが一般的です。
また、賃貸契約のあいだは住宅ローン控除が適用されません。
賃貸契約が終わったあとに、残存期間があれば再度適用可能です◎ ※再度手続きが必要
4. インフレ時代の資産防衛になる
近年、世界的にインフレが進行しており、日本でも物価上昇が続いています。



生活コストは確実に上がっていますよね
固定金利で住宅ローンを組めば、毎月の返済額は変わりません。
インフレで給与が上がれば、相対的にローン返済の負担感が減ります。
また、不動産という実物資産を持つことで、インフレによる貨幣価値の目減りから資産を守ることができます。



お金の価値が下がっても、不動産の価値は維持されやすいです
賃貸の場合、インフレに伴って家賃が上昇するリスクがありますが、住宅ローンの返済額は固定金利なら変わりません。
長期的な視点で見れば、マイホームを持つことが資産防衛策になります。



わが家も固定金利で住宅ローンを組んでいるため、今後不安になることなく安心です
5. 団体信用生命保険で家族を守れる
住宅ローンを組む際にほとんどの場合加入するのが、団体信用生命保険。
万が一、契約者が死亡または高度障害状態になった場合、残りのローンが保険で完済されます。



マイホームは生命保険の機能も兼ね備えているのです!
家族に負債を残さず、住む場所を確保できる。これは家族を守る大きな保険になります。
別途高額な生命保険に加入する必要性も減るため、保険料の節約にもつながりますよ◎
トータルで見れば、賃貸生活よりも経済的に有利になるケースが多いのです。
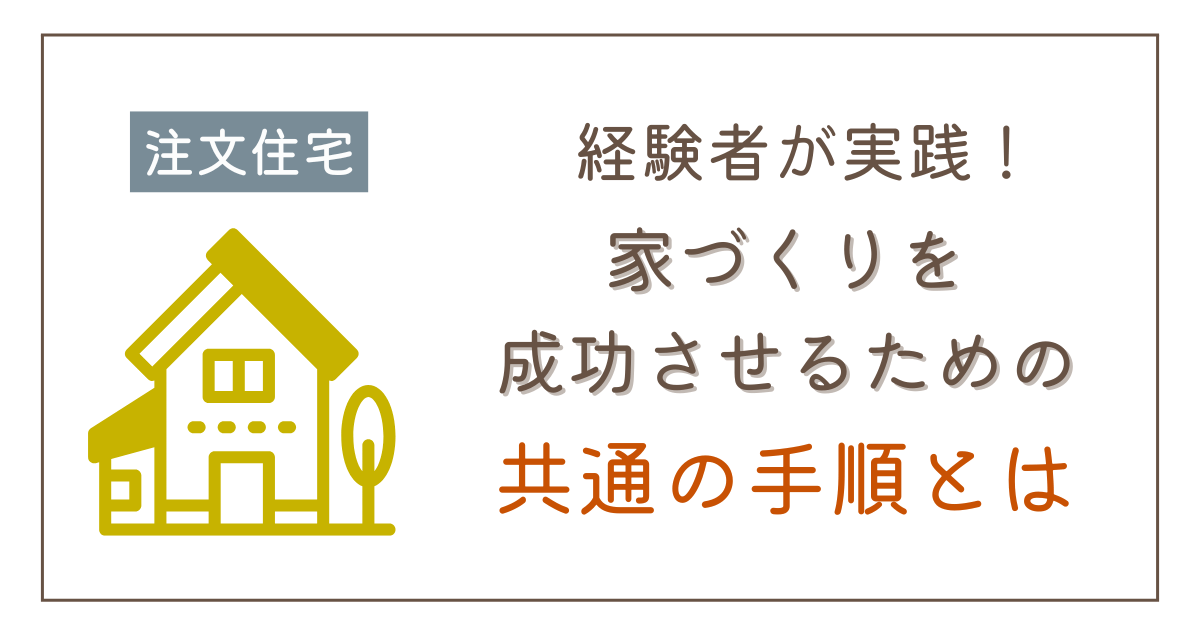
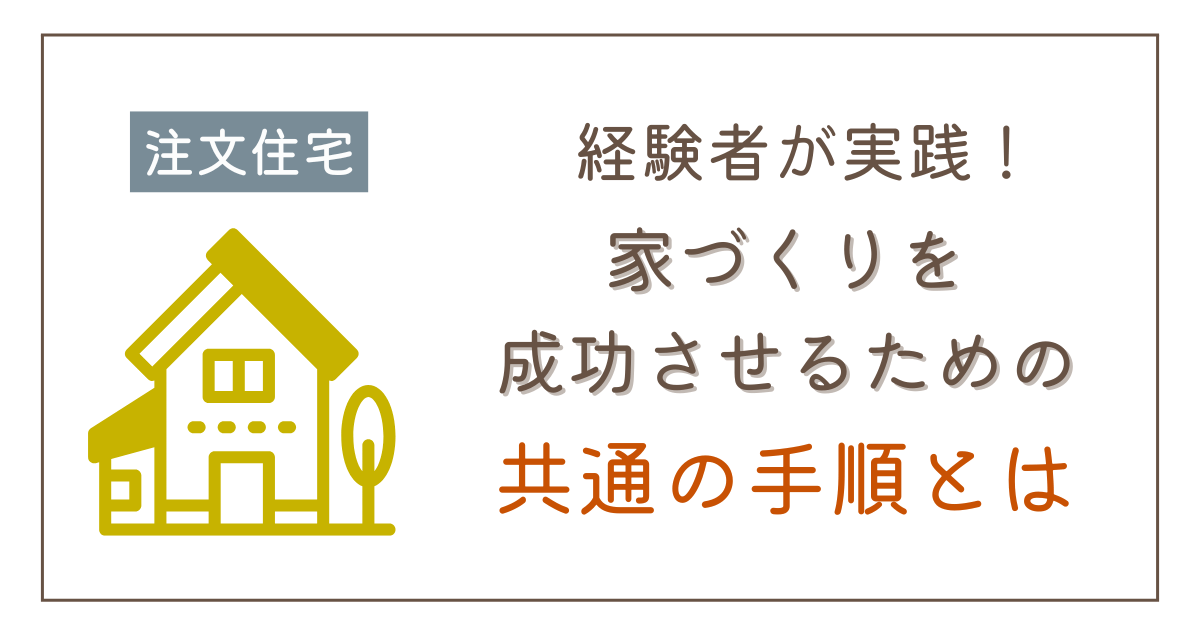


“定年後に一括購入”が危険な3つの理由
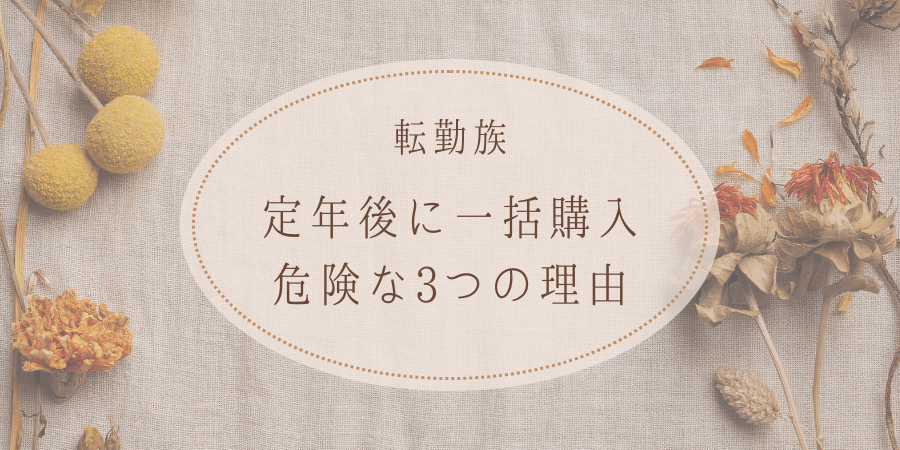
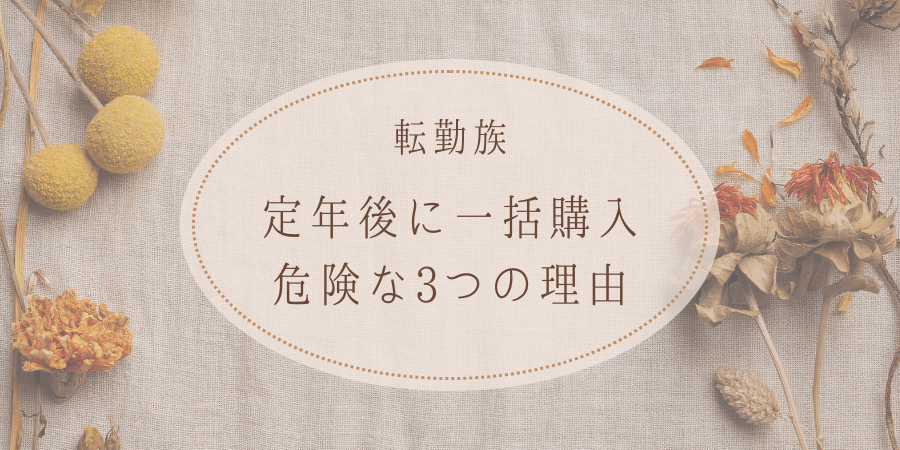
“定年まで賃貸で、退職金で一括購入すればいい”という考え方には、実は大きなリスクが潜んでいます。
理由1.退職金が予定通り出る保証はない
終身雇用や年功序列が崩れつつある現代、退職金制度も変化しています。
- 会社の業績悪化
- 早期退職の推奨
- 退職金制度の改定 など



こういった理由から、予定していた金額が出ない可能性は十分にあります
また、定年までの間に親の介護・子どもの教育費・病気など、想定外の出費が発生することも。
退職金を住宅購入以外に使わざるを得ない状況になるかもしれません。
“定年後に一括購入”という計画は、あまりにも不確実な未来に依存しています。
理由2.高齢になってからの住宅購入は困難
60歳を過ぎると、賃貸でも購入でも選択肢が大幅に狭まります。
賃貸の場合、高齢者への貸し渋りが現実問題として存在します。



孤独死のリスクや家賃支払い能力への不安から、断られるケースが増えています
購入しようにも、年齢や健康状態によって住宅ローンが組めない場合があります。
団体信用生命保険への加入には健康状態の告知が必要で、持病があると加入できません。
現金一括購入できる資金があればいいですが、それでも高齢になってからの住宅探し・引越し・新しい環境への適応は、肉体的にも精神的にも大きな負担です。
理由3.若い時期の住宅ローンメリットを逃す
住宅ローンは若いうちに組むほど有利です。
40代前半までに購入すれば、35年ローンでも問題なく組めます。
完済時年齢が80歳未満であれば、審査も通りやすく、借入可能額も多くなります。
また、住宅ローン減税の恩恵を長期間受けられます。
40歳で購入すれば13年間、最大400万円以上の税制優遇を受けられますが、定年後に購入すればこの恩恵は得られません。
さらに、早期に購入して賃貸に出せば、その期間の家賃収入でローンを返済できます。
結果的に、実質負担を大幅に減らせます◎
定年まで待つことは、これらすべてのメリットを放棄することを意味します。



時間を味方につけることが、資産形成においては非常に重要です!
転勤族のマイホーム購入|成功する人と失敗する人の違い
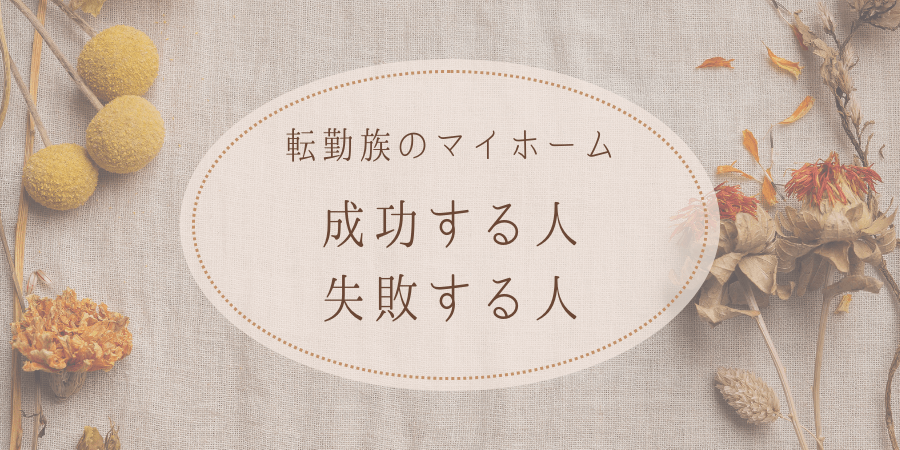
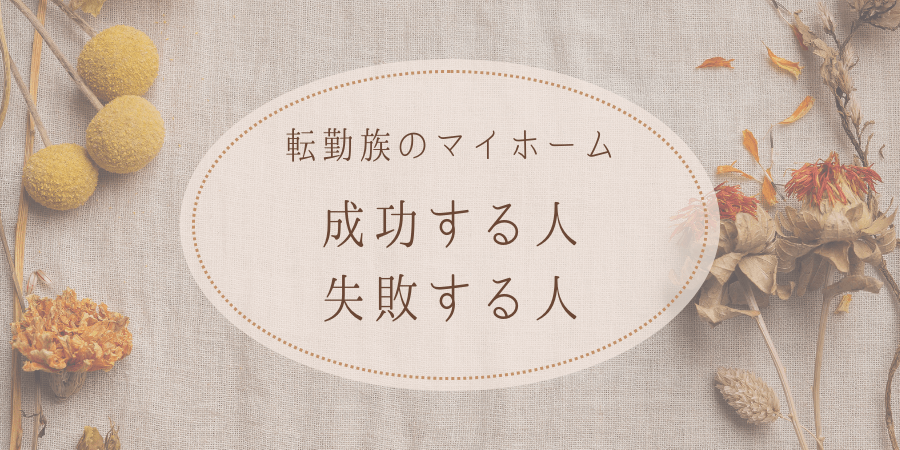
転勤族でマイホームを購入して成功する人と失敗する人には、実は明確な違いがあります。
成功する人の特徴
立地選びを最優先する
成功する人は、自分が住まない期間も賃貸需要がある場所を選びます。
- 都市部へのアクセスが良い駅近物件
- 学校や商業施設が充実した生活利便性の高いエリア
- 治安が良く住環境として人気のある地域 など
また、一時的に住まない期間があったとしても、
- 将来的に自分が住みたいと思える場所
- 親の介護なども視野に入れた実家近くのエリア



こういった長期的な視点で立地を選ぶと後悔しにくいです◎
賃貸管理の体制を整える
信頼できる不動産管理会社を見つけ、転勤前から関係を構築するのも賢い方法です。
- 入居者募集
- 契約手続き
- トラブル対応 など



これらを任せられる体制を整えておくと安心
また、維持管理しやすい設備や内装を選び、シンプルで普遍的なデザインにすることは、空室リスクを減らすことにつながります。
保守的な資金計画を立てる
家賃収入をあてにしすぎず、自己資金だけでも返済できる範囲で借り入れています。
空室期間・家賃相場の変動リスクなども考慮した上で、無理のない返済計画を立てましょう!
頭金も多めに用意し、借入額を減らすことで毎月の返済負担を軽減することができます。



万が一の事態にも対応できるようにしたいですね
失敗する人の特徴
立地を妥協して安い物件を選ぶ
価格だけで判断し、駅から遠い・周辺環境が良くないなど、立地を妥協するパターン。
この場合、転勤中に借り手が見つからず、空室が続いて経済的負担が増大してしまうリスクがあります。
賃貸管理を軽視する
遠方からの管理を甘く見て、適切な管理会社を選ばなかったり、自分で管理しようとしたりします。
この場合、対応が遅れて入居者とのトラブルや物件の劣化を招きかねません。
ギリギリの資金計画を立てる
家賃収入を前提に、限界まで借り入れてしまうパターン。
この場合、空室期間が発生したり予想外の修繕費が必要になったりすると、返済が困難になってしまいます。



最悪の場合は売却することに・・
成功と失敗を分けるのは、リスクを正しく理解し、それに対する備えをしているかどうかです。
定年まで賃貸か早期購入か|あなたに最適な選択は?
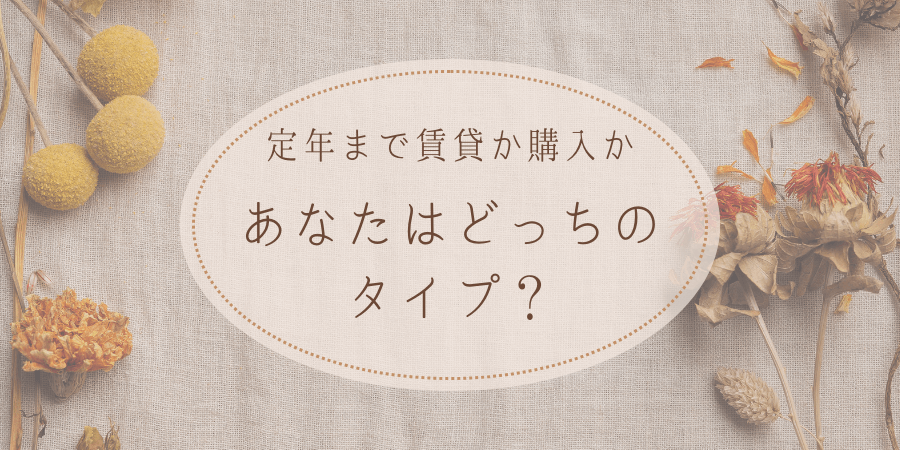
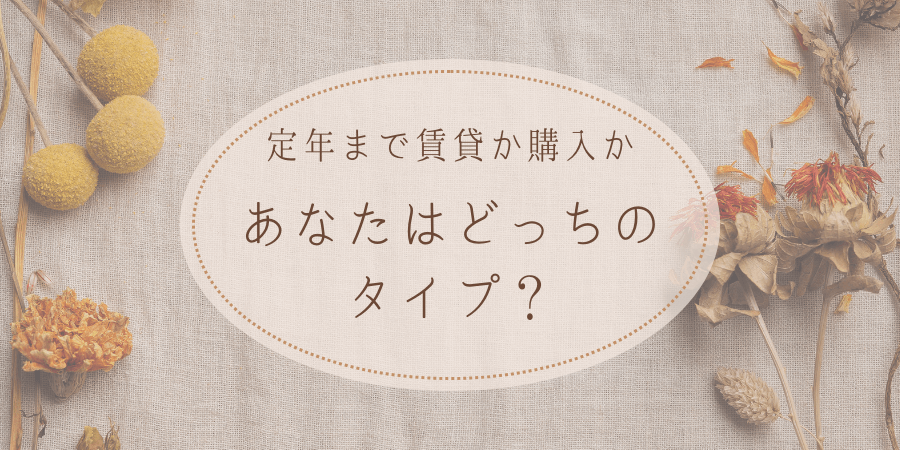
ここまで、転勤族が”定年まで賃貸”を選ぶべきか、早期購入すべきかを様々な角度から比較してきました。
定年まで賃貸が向いている人
- 転勤頻度が非常に高く、数年ごとに全国を移動する
- 将来住みたい場所が全く定まっていない
- 住宅購入や管理の手間を絶対に避けたい
- リスクを取りたくない性格



これらに当てはまる方は、無理にマイホームを購入する必要はありません
ただし、インフレリスクや老後の住居確保については、別の方法で対策を講じる必要があります。
早期購入が向いている人
- 家族に安定した生活を提供したい
- 資産形成を真剣に考えている
- 将来住みたい地域が決まっている
- 賃貸管理などの手間を許容できる
- 計画的にリスク管理ができる



これらに当てはまる方は、定年を待たずにマイホーム購入を検討する価値があります
特に40代前半までの方は、時間を味方につけることで大きなメリットを得られますよ◎
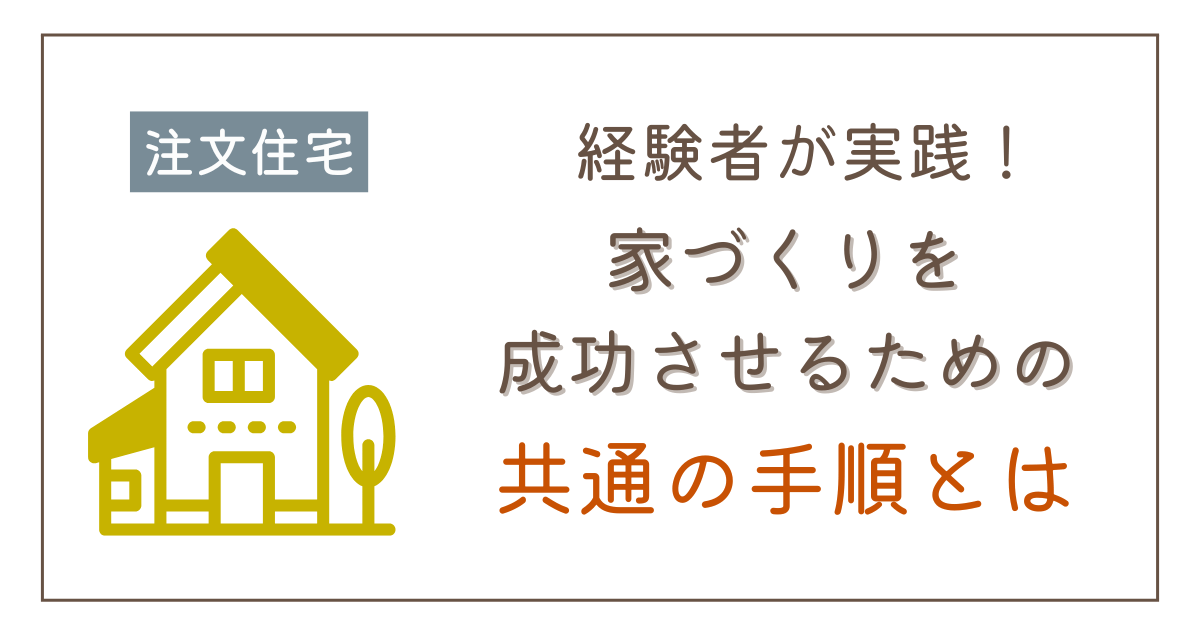
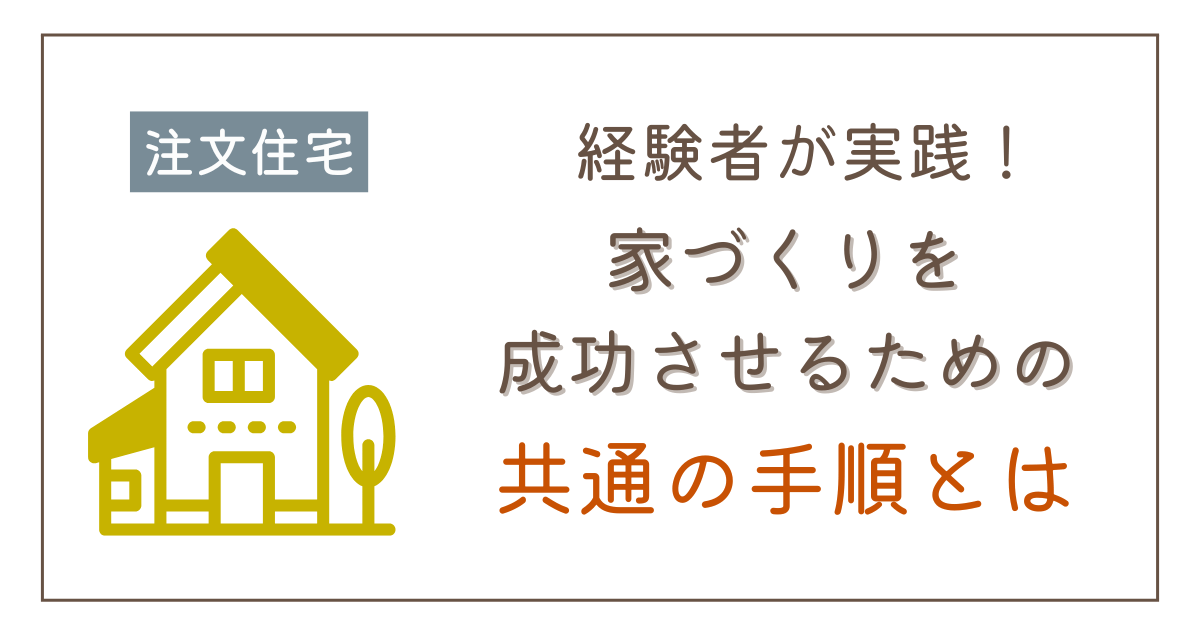


一歩踏み出す勇気が未来を変える!
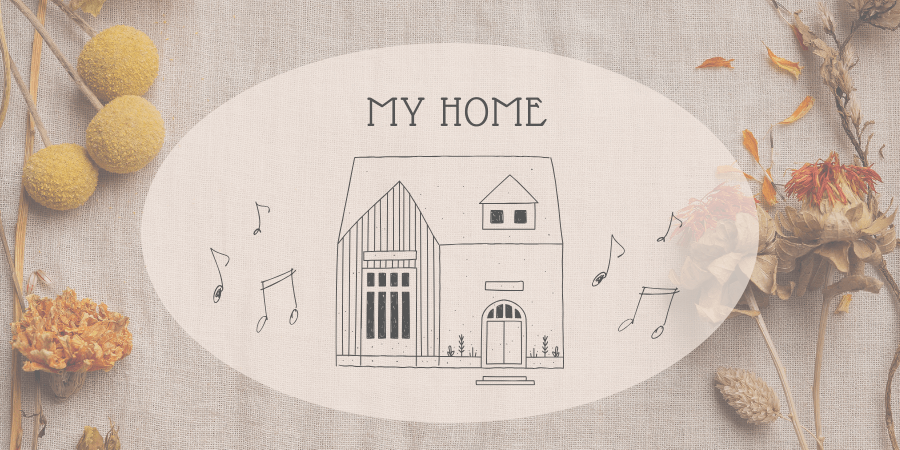
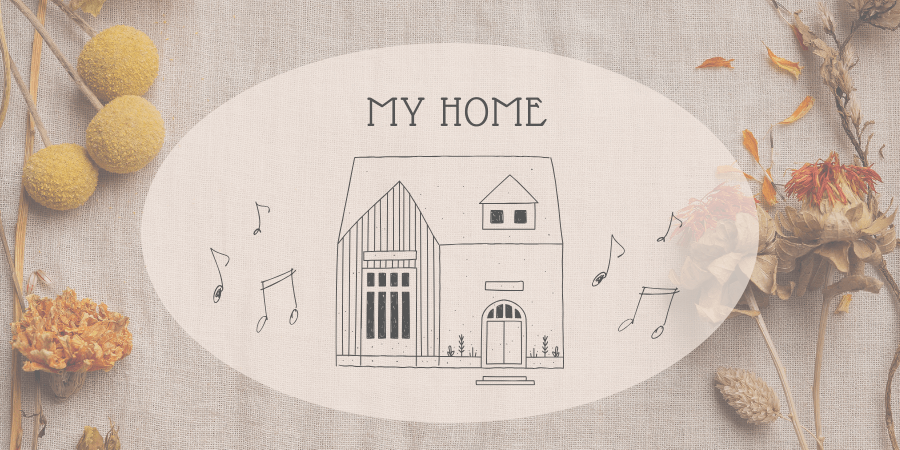
- 転勤族だからマイホームは無理
- 定年まで賃貸でいい
そんな固定観念を、一度見直してみませんか?
確かにリスクはあります。
しかし、人生において完全にリスクのない選択など存在しません。
大事なのは、リスクを理解した上でメリットと天秤にかけ、自分と家族にとって最善の選択をすることです。
- 30年間で3,600万円を支払っても何も残らない賃貸生活
- 同じ金額を投資して2,000万円以上の資産と家族の安定を手に入れる選択。



どちらがあなたの人生にとって価値があるでしょうか?
定年を待つ必要はありません。
今、この瞬間から始められます!
家族と話し合い・情報を集め・信頼できる専門家に相談する。
そこから全てが始まります。
転勤族だからこそ、マイホームという帰る場所を持つ意味は大きいです。
あなたと家族の未来のために、一歩踏み出す勇気を持ってみてください。
その決断が、10年後・20年後のあなたに大きな安心と満足をもたらすはずですよ◎
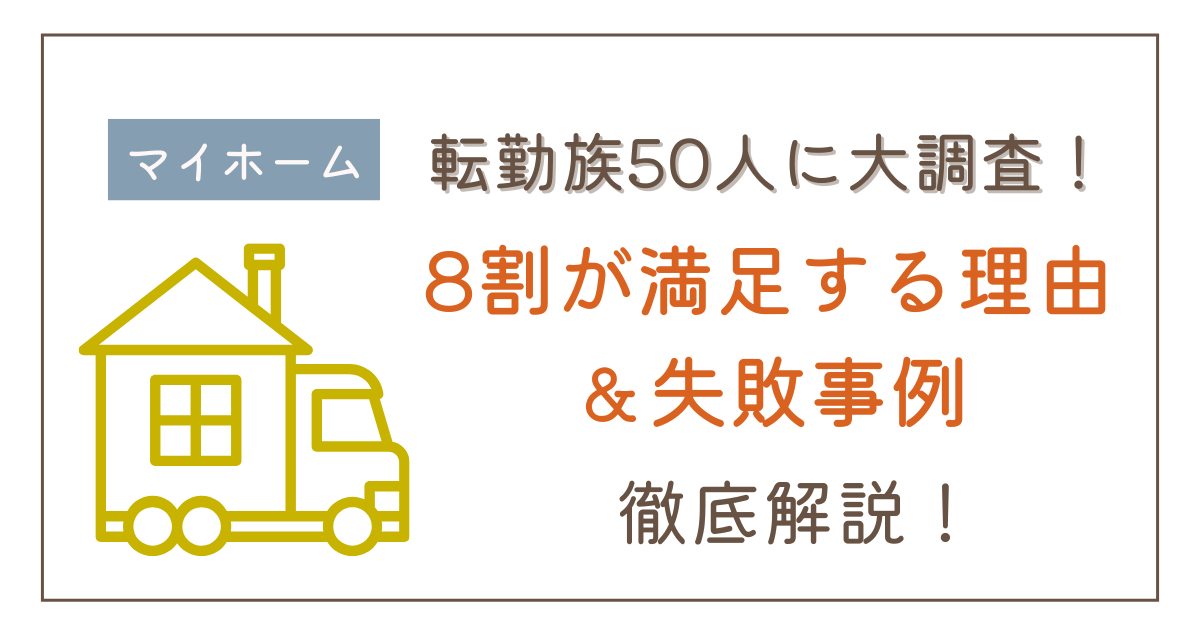
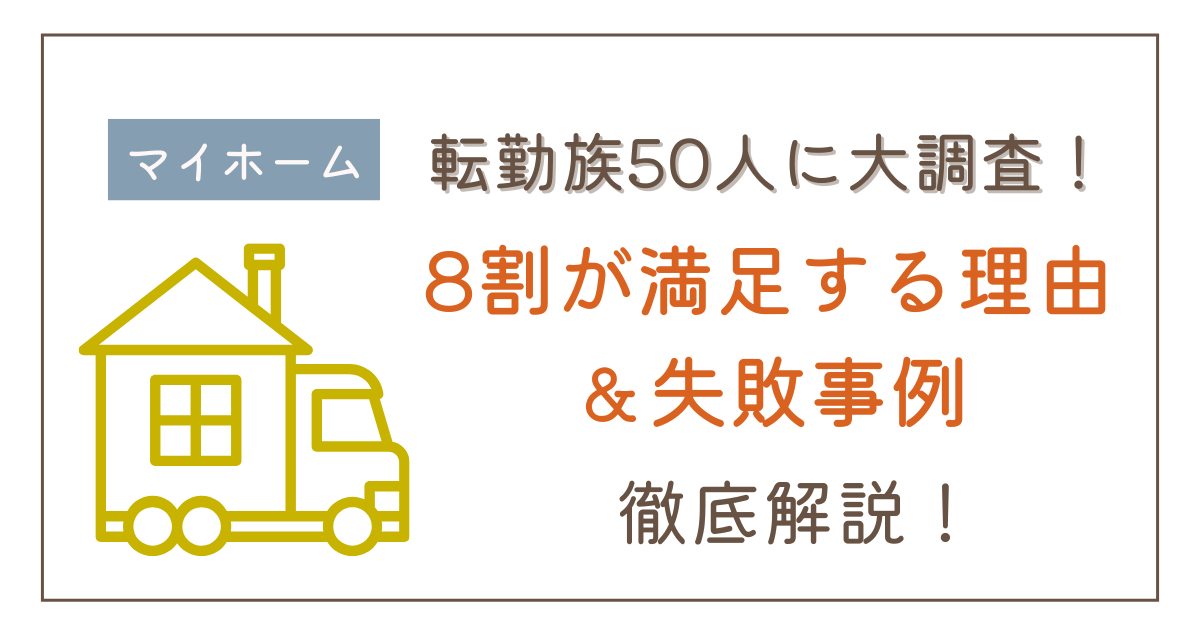
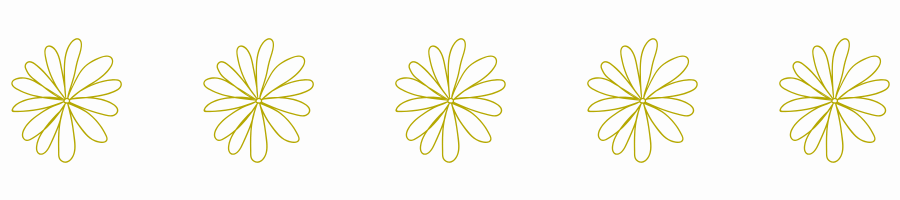
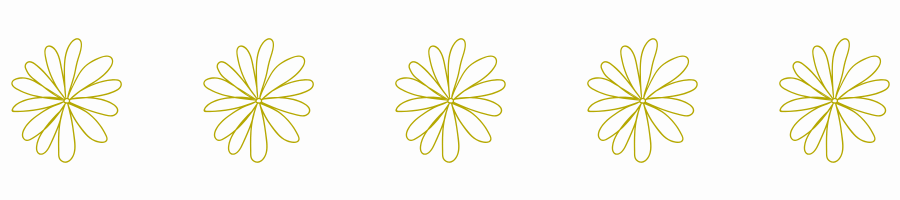
具体的なマイホーム計画の進め方はこちら